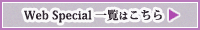講演
「セルタネージャ・ミュージックとブラジル音楽事情
――ネルソン・ペレイラ・ドス・サントス 講演と上映シリーズ」
2002年7月12日
国安真奈(通訳・翻訳者・ライター)
今日はセルタネージャ・ミュージックのお話をしにやってまいりました。セルタネージャという音楽のことを話す前に、少しブラジルのことをお話したいと思います。ここにお集りの方々はたぶんご存知でしょうが、ブラジルは南米で唯一、ポルトガル語が公用語の国です。周りがみんなスペイン語を使う国なので、少し孤立した文化が発達した国です。古くから人種間、民族間の混血が盛んで、入植者の白人と、先住民と、アフリカから連れてこられた黒人奴隷、それから少し後になって移民してきた黄色人種たちが盛んに混血しました。そういった国なので非常にユニークな文化が形成されたのですが、ブラジルはとても広い国なのでそれは単一ではなく、地域によってそれぞれ異なる文化が発達しています。ブラジルの国土は日本の23倍です。とにかく広い。東京のような都会もあれば、何も無い土地が延々と広がっている場所もあり、どちらかと言えば、人が住んでいる土地よりも人が住んでいない土地の方がたくさんある国です。町と町は日本のように近接していません。ある町を出ると次の町までは誰も住んでいない空間が広がっていて、これは日本では見られない光景だなあ、と思います。町と町の間の主な交通手段は長距離バスか飛行機です。町には必ずバスターミナルがあって、日本の高速バスと言うよりはアメリカのグレイハウンドバスのような大きなバスがあちこちに向けて走っている。この後で上映いたします『人生の道~ミリオナリオとジョゼ・リコ』にも映っていますので、ぜひお確かめください。
そのような国ですので、音楽もたくさんの種類がありまして、地域によって多種多様です。日本でブラジル音楽と言えば、ボサノヴァやサンバをイメージされる方は多いと思いますが、このふたつはリオの都会で発達した音楽で、ブラジル音楽のなかのごく一部にすぎません。今日、皆さんがご覧になる『人生の道~ミリオナリオとジョゼ・リコ』で聴くことができる音楽は、ムージカ・セルタネージャとかムージカ・カイピーラと呼ばれるジャンルです。カイピーラとはサン・パウロ州のスラングで「田舎」のことですので、田舎の音楽といった意味になります。サン・パウロ州を中心にミナスジェライス州、パラナ州、バイーアの南の方、リオの一部、それからマット・グロッソにまたがって、かなり広範な地域になりますが、そういう地方の田舎で伝えられてきた音楽です。そういった所はインテリオールと呼ばれています。海岸部に対する内陸部、という呼び名ですが、要するに農村地帯です。牧草地などがある所に人々が集落をつくって住んでいる。アメリカの農業地帯を想像していただいたらよろしいかと思います。ムージカ・セルタネージャにつきましても、カントリー・ミュージックのブラジル版だとイメージしてください。そういった音楽が好まれているブラジルの農村地帯にはカウボーイがたくさんいまして、彼らの外見やスタイルはアメリカのカウボーイそのままなんですね。ロデオ大会もよくやっていますし、サーカスの巡業があったり、カントリー・フェアと言うのでしょうか、農産物の展示会、見本市が行われたり、いわゆる田舎のお祭りなんですけど、そういった会場に欠かせないのがセルタネージャ・ミュージックのライヴなんです。
そのセルタネージャ・ミュージックを先ほどブラジルのカントリー・ミュージックと申し上げましたが、やはり違うところもありまして、そのルーツを調べていたら面白いことが分かったのでご紹介いたします。セルタネージャ・ミュージックは主に1920年代頃から一般的に知られるようになってきたと言われています。ただ、それ以前から、モーダ・ヂ・ヴィオラという名で呼ばれていた音楽がありまして、これが元になってセルタネージャ・ミュージックが生まれたらしいのです。モーダ・ヂ・ヴィオラとは、ヴィオラを使う音楽という意味ですが、このヴィオラは日本で言うところのヴィオラ、ヴァイオリンに似た楽器ではなくて、ギターもしくはマンドリンのような楽器で、二本ずつ五組のスチール弦を張るとてもきれいな音のする楽器です。セルタネージャ・ミュージックで使われるのは、特にヴィオラ・セルタネージャ、ヴィオラ・カイピーラと呼ばれるものです。これはルネッサンスの頃にポルトガルやスペイン、イベリア半島で発達した楽器が元になっているそうです。これをポルトガル出身の植民者がブラジルに持ち込み、それが現在まで伝わっている。ここで、この楽器の音を聞いていただこうと思います。CDの一曲目をかけてください。
(「BAIÃO DO PÉ RACHADO」)
ブラジルの有名なヴィオラ奏者で研究者でもあるホベルト・コヘイアの「Uróboro」というアルバムの一曲でした。この楽器などを使って歌われてきた音楽がセルタネージャ・ミュージックのベースになったわけです。このセルタネージャ・ミュージックがまだモーダ・ヂ・ヴィオラだった時代は、ポルトガルの宗教的な歌や、先住民の伝説とかをモチーフとした歌詞を歌っていたそうです。聖書の一場面を歌にして田舎の教会で皆に聴かせたりしていたそうで、その時代が四世紀も続きました。歌詞のモチーフはだいたい聖書なんですが、どこかブラジル的なものが多いです。ひとつご紹介したいと思います。
「猿の誕生」
私たちは猿の肉を食べるべきではない。なぜなら猿は人間の親戚だからね。
猿はこんなふうに生まれてきたのだよ。
あるときイエス様が聖ペテロと旅をされていて、ある鍛冶屋にたどりついた。
そして鍛冶屋に「馬に蹄鉄をつけられるかね」とお尋ねになった。
すると鍛冶屋は「できますとも。わしは腕では誰にも負けない」と言った。
するとイエス様は聖ペテロに命じて火を熾させ蹄鉄を打たせた。
そして真っ赤に灼けた蹄鉄を手でおつかみになり、馬の蹄におつけになった。
鍛冶屋はそれを見て、これはすごい、と思った。
別の日にイエス様と聖ペテロが同じ鍛冶屋を訪れ、
近所に住んでいる老夫婦を呼んでくれと言った。
老夫婦がやって来ると、イエス様は爺さんをつかまえて炉のなかへ入れ、
爺さんが真っ赤になると取り出して、金床の上でこれを打ち延ばした。
すると爺さんは背筋もピンと伸びて、つややかで美しい若者になった。
爺さんが鍛冶屋を出ると村の娘たちが先を争って誘いにやってきた。
イエス様はおなじことを婆さんにもしてあげようとしたが、
婆さんのほうは怖くなってしまって遠慮した。
けれどもイエス様と聖ペテロが行ってしまうと、
鍛冶屋は自分も同じことが出来ると証明したくなって、
婆さんを炉のなかへ入れ、真っ赤になったところを金床の上で打ちのばした。
打って打って打ち延ばしたら若い娘にならないで、
婆さんは顔の赤い猿になってしまった。
これは神様の罰だったのだよ。
婆さんはイエス様を信じなかったし、鍛冶屋はイエス様と同じになろうとした。
こうして猿はこの世にやってきたのさ。
だから猿の肉を食べてはいけないよ。
もともとは私たちと同じ人間だったのだからね。
こんなブラジル的なお話なんですけれども、モーダ・ヂ・ヴィオラは、こういった素朴なお話を歌い伝える、民謡のようなものを音楽だったのが、時代の推移とともにそのテーマが変化していって、農村地帯の開墾者たちの冒険譚とかになっていきます。これがだいたい1920年代くらいです。コルネリオ・ピレスというジャーナリストがいまして、開墾者たちの物語を歌ったこの時代の歌詞をたくさん採集して、「ジョアキン・ベンチーニョの奇妙な冒険」という本にまとめています。このコルネリオ・ピレスはセルタネージャ・ミュージックの歴史において大きな役割を果たした人で、現代のセルタネージャ・ミュージックの始祖と言えるトニッコ・イ・チノッコ、トニッコさんとチノッコさんのふたり組ですが、彼らを発掘した人でもあります。コルネリオ・ピレスはサン・パウロ州の内陸部でこのコンビを発掘して、他にもアウヴァレンガ・イ・ハンシーニョとか幾つかコンビを発掘して、彼らをサン・パウロの都会へ連れてきて、レコードを吹き込ませようと考えたんです。ところが、サン・パウロのレコード会社を訪ね歩いてみたところ、どの会社もノッてくれない。でも、コルネリオ・ピレスはどうしてもレコーディングさせたいと思い、1929年についに自分でお金を出して彼らの歌をレコーディングするんですね。今で言うインディーズ・プロダクションです。このレコードがきっかけとなって、しばらくすると彼らの音楽はブラジル各地のラジオで流れるようになりました。そして、その成功にあてこんで、それから無数のコンビが誕生します。セルタネージャ・ミュージックのコンビは本当にたくさんいます。それまでは田舎でしか聴かれていなかったセルタネージャ・ミュージックが、これはビジネスになるんじゃないか、と50年代に盛んにレコードが作られるようになり、ラジオでも歌われるようになりました。その時代のラジオは実況中継放送ですから、スタジオやホールでライブで歌うわけです。それで、都会の人々も聴きはじめたことから、歌のテーマも田舎の日常だけではなくて恋だとか人生だとか、より多くの人に通じる、身近で普遍的なテーマが歌われるようになってきました。もうひとつ面白いこととして、1950年代にセルタネージャ・ミュージックがワーッと世の中に広がっていくわけですけれども、この頃に、パラグアイのフォルクローレ、グアラニアと言いますが、グアラニアの有名な曲をセルタネージャ風にレコーディングしてブラジルで大ヒット、といったこともあったようです。
これまでお話してきたように、セルタネージャ・ミュージックは基本的にはコンビで歌うんですけれども、ソロで活躍している人もいます。有名なのはセルジオ・ヘイスとかイネス・ヂ・バホス、この人は女性ですが、そういった人たちがいます。だいたい1960年代ぐらいまでのスタイルがトラディショナルとかルーツとされています。その後、過渡期があって、80年代になるとアメリカのカントリー・ミュージックの影響を受けたセルタネージャ・ミュージックがすごく多くなりました。それからメキシコ風の音楽に影響を受けたスタイルも流行して、若いメガヒットスターが現れたりしています。それまではブラジルのアコースティック・ギター、ヴィオラゥンと言いますけれども、それを弾いて歌っていたのが、それに代わってエレキギターをガンガン鳴らして、スタジアムでライヴをやってしまうようなセルタネージャ・ミュージックもあります。若い歌手ですからアイドル的なロマンティックなラヴソングが多くて、これを最近はセルタネージャ・エレクトロニカ、エレキ・セルタネージャなどと呼んでいます。本当に今風の音楽で、どこがセルタネージャなのかよく分からない感じですけれども、コンビで歌うというスタイルは維持されているようです。代表的なスターとしては、レアンドロ・イ・レオナルドとかがいます。ちなみに、レアンドロ・イ・レオナルドは一枚のアルバムが300万枚近く売れる大スターです。エレキ・セルタネージャは大変な人気で、現在では音楽CDのすべての売り上げの六割を占めるほどです。かなり大きなマーケットになっています。
これから皆さんがご覧になる映画に登場するミリオナリオ・イ・ジョゼ・リコ(ヒコ)、ミリオナリオとジョゼ・リコ(ヒコ)のふたりは実在する人気ミュージシャンです。60年代ぐらいまでのルーツと呼ばれるセルタネージャ・ミュージックと80年代以降のエレキ・セルタネージャの間ぐらいに位置する人たちで、トラディショナルな感じでありながら普遍的な現代的な歌詞を歌っています。残念なことに、現在、エレキ・セルタネージャが大ブレイクしていて、セルタネージャ=子どもが聴く音楽、という図式が一般的になってきました。元々、田舎の音楽という偏見があったりしたために、そういった一方的な図式化がますます助長されています。そうじゃない音楽を頑張っているミュージシャンもたくさんいるんですけどね。ちなみに、昨年、『人生の道~ミリオナリオとジョゼ・リコ』が上映されたときにネルソン・ペレイラ・ドス・サントス監督が舞台挨拶にいらして、ブラジル人の記者が「監督は都会の方なのに、なぜセルタネージャ・ミュージックを題材にとりあげたのですか?」という質問をしたんです。監督は、父がサンパウロのインテリオール出身でセルタネージャ・ミュージックをこよなく愛していた、だからこの作品は父へのオマージュでもある、とお答えになっていました。そして、僕自身はもっと都会的な音楽のファンだ、と笑いながら仰っていましたね。
さて、大変お待たせしましたが、ここからようやく『人生の道~ミリオナリオとジョゼ・リコ』のお話です。ミリオナリオ・イ・ジョゼ・リコ(ヒコ)のふたりが主人公なわけですが、まず面白いのが彼らの名前です。ミリオナリオは「百万長者」という意味で、ジョゼ・リコの「リコ」は英語で言うところの「リッチ」ですから、ジョゼ・リコとは「金持ち太郎」とでも言うような名前ですね。セルタネージャ・ミュージックはコンビがお決まりですが、そのコンビ名は並べたときに音の感じが良いとか、似たような意味とか、対比になっているとか、そんな感じで付けられている場合が多いです。例を挙げますと、レアンドロ・イ・レオナルドとか、ジアン・イ・ジオバンニ、テオドーロ・イ・サンパイオ。テオドーロ・イ・サンパイオとは、テオドール・サンパイオというブラジル史上の偉人の名前をふたりで分け合っているコンビ名なんですね。音の関連性より意味を関連づける方が難しいみたいで、その点、ミリオナリオ・イ・ジョゼ・リコは非常にユニークな名前です。やすし・きよしとか星セント・ルイスとか、かつての漫才コンビの名前のノリにも似ていますね。ジョゼ・リコの本名はジョゼ・アウグストス・サントスでして、「リコ」はどこにもありません。1948年にパラナ州のテーハ・リカ(ヒカ)という所で生まれたそうです。このテーハ・リカ(ヒカ)とは「豊かな土地」という意味で、そこの出身だからあだ名が「ジョゼ・リコ(ヒコ)」だったらしく、それを芸名にしたんだそうです。その彼が出会ったミリナリオの本名はホメオ・ジャヌアリオ・マトスで、これまたどこにも「ミリナリオ」はありません。1940年にマット・グロッソ州のモンテサンチスという所の生まれで、お前がリコ(ヒコ)=金持ちなら俺はミリナリオ=百万長者だ、ということでミリナリオという芸名にしたそうです。サングラスをかけている方がジョゼ・リコさんで、おじさんっぽい感じの人がミリナリオさんです。彼らは、この映画で描かれているとおり、音楽ビジネスの中心はサン・パウロだということで、サンパウロに出てきて、ダウンタウンの安宿に滞在し、そこで出会って、1970年頃にコンビとしての活動を開始したそうです。ジョゼ・リコはしばらく前からサン・パウロにいたんですが、ずっとチャンスとパートナーに恵まれず、ミリナリオと出会う前にコンビの相方を8人も取り替えています。
この映画では、彼らのキャリアの初期の時代がユーモアたっぷりに描かれています。現在、彼らはキャリア30年以上の大ベテランで25枚ものアルバムを発表していますが、なかでも5枚目の " Estrada da Vida (人生の道)" が大ヒットして、全国的に有名になりました。その収録曲は今でもライブのレパートリーになっていて、歌わないとお客さんが納得しないそうです。彼らは芸人に徹しているところがあって、各巡業先の地域的な文化や風俗、特色を取り入れた曲を演奏し、アレンジを施して、その土地で一番ウケるようなライヴをするんです。南の方に行けばグアラニアを取り入れた曲をたくさん演奏したり、ハンシエラというジャンルがあるんですが、それが人気のある地方ではそれを演奏し、ボレロを歌ったり、その結果、彼らは他のジャンルの要素を取り入れた幅のあるセルタネージャ・ミュージックを新しく作っていくことになります。91年に彼らは活動を一時休止し、コンビを解消します。ミリナリオは他のパートナーとコンビを組み、ジョゼ・リコはソロアルバムを出したりしました。でも、オン・ザ・ロードが自分たちの音楽人生、と思い返したのか、ふたりは再結成し、今はかつてと同じように精力的に巡業公演をこなしています。現在も彼らはツアー、と言うより巡業の真っ最中で、たとえば7月5日は、サン・パウロ州のセルタンジーニョという所の農牧畜フェア会場で演奏しています。翌日6日は、5000キロぐらい離れているでしょうか、マラニョン州のインペラトリスの農牧畜フェアで演奏。その翌日は、バイーア州ベヘーラスの農牧畜フェアで演奏。11日は、ミナスジェライス州のチーズフェア特設会場でライヴ。今日12日は、ゴイアス州インパメリという所でライヴをやっているはずです。これらの地名のうちインペラトリスぐらいしか私は知りません。大都会がひとつも入っていないですね。ツアーと言うより、内陸部の小さな都市を丁寧に巡回していくやり方ですね。まさに " Estrada da Vida " といった感じの活動を続けています。というところで、ふたりの紹介を終えたいと思います。後は映画をごゆっくりお楽しみください。どうもありがとうございました。