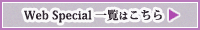トーク「罪の天使たち」
2009年12月10日
諏訪敦彦(映画作家)
ブレッソンの映画について語るのは荷が重いのですけれども、私が映画を作るうえでブレッソンがどういう存在だったかを少しお話しできればと思っています。
僕にとってのブレッソンの映画とは、『やさしい女』のドミニク・サンダとか、『白夜』のイザベル・ヴァンガルデンとか、『バルタザールどこへ行く』のアンヌ・ヴィアゼムスキーとか、こういう女優たちですね。ご存知のように、ブレッソンはある時点から、徹底して映画に出演したことがない素人を役者に起用します。今、申し上げた女優たちは、その後、女優としてのキャリアを続けた人もいれば、そうしなかった人もいるのですが、彼女たちの最初の出演作を撮ったのがブレッソンなわけです。そのブレッソンの映画における彼女たちの存在感、これはもう本当に衝撃的で、僕にとっては忘れられない女優たちになりましたね。この彼女たちの演技は他の監督の映画では絶対にありえないもので、現実的な本当らしさがまったくない。われわれは字幕を読んでいるのでよく分からないところもあるのですけれども、台詞もかなり棒読みに近い。感情がまったく込められていない。表情も非常に硬く、頑に何かを拒絶している存在として女性たちが描かれている。その存在がとても印象的だったんですね。
僕が学生時代に「作家主義」という本が出版されまして、これはインタビュー集なんですけれども、最近は本屋で見かけませんがお読みになった方もいるかもしれません。そこに有名なゴダールからブレッソンへのインタビューが掲載されているんですね。これは非常に面白いインタビューでして、とにかくブレッソンは職業俳優はダメだと言い張るんです。こいつらはどうしようもない、身につけてしまったものを剥ぎ取るだけで大変な苦労だと。そんな苦労をするぐらいだったら、非職業的な俳優を起用した方がよいと頑として譲らない。ゴダールはそんなブレッソンに食らいついて、質問を投げかけるんですね。しかし、俳優であっても俳優という職業のひとりの人間でしょ、だから人間であることにおいて変わりはないんじゃないか、演技を仕事とする人間として描く方法があるんではないですか、とゴダールはブレッソン大先輩に言うんですね。ところがブレッソンは、いや絶対そんなことはない、そう思うなら君はやってみたまえ、しかし徒労に終わるだろうと徹底的に職業俳優を拒絶しています。僕はどちらかと言うとゴダールの意見に賛同しました。監督になってからも僕は俳優とコラボレーションしてしまいますし、俳優に関心があります。俳優を職業として選ぶ人たちに興味がありますし、だから、俳優たちが演技によって表現する内容だけでなく、それをやろうとしている彼、彼女たちに関心がある、と自分では思っています。
最近、『ユキとニナ』という映画を作りまして、一月に公開なんですけど、その撮影のときのお話を少ししたいと思います。僕はブレッソンの映画の俳優の存在感に強く衝撃を受けたんですけれども、彼の映画の特徴はそれだけではなくて、例えば、クローズアップが多用されて、ひとつひとつのショットがうまく繋がらないということもあると思います。普通の映画なら、バラバラのショットを想像で繋ぎ合わすことができて、このシーンはこういうことが起きているんだなということが苦もなく理解できるわけです。それは皆さんが子どもの頃から映像を見慣れているから、映像を見ることが習慣化されているからでもあるわけですが、ブレッソンの映画はショットとショットが断絶されていて、うまく繋がらない。僕はショットとショットをあまり分断しないで、バラバラにしないで映画を作ってきた。モンタージュに関して、いわばブレッソンとは逆の立場なので、映画を作っているときにブレッソンを意識することはほとんど無いんですけれども、『ユキとニナ』を撮影しているときにこんなことがあったんです。『ユキとニナ』はその当時8歳の女の子が主人公で、その女の子は映画に出演するのがはじめてだったんですね。映画の後半は、女の子が家出をして、森のなかに迷いこむというストーリーなんですが、最初は親友のニナと森に入って行くんですけれども、はなればなれになって、ひとりぼっちになる。そこで極限の孤独を感じて、寂しくて泣いてしまう。そう脚本には書かれていたんです。けれども森のなかの撮影が進んで、いよいよそのシーンを撮るといったときに、そのユキを演じたノエちゃんが、私は泣いたりできない、と言うんですね。悲しい気持ちになりたくないし、そういうふりをすることも私にはできないと言ったんですね。できないし、やりたくないと言ったんです。それで、僕たちは困ったんですね。ユキという女の子が物語のなかで本当の孤独、辛さを表現しなければ、この映画は成立しないんじゃないか、とそのときは思ったんです。それで、さあどうしようかということで、キアロスタミのように無理矢理泣かす方法も可能性としてはあって、『友だちのうちはどこ?』でキアロスタミは子どもの目の前で彼が一番好きな俳優かなんかのピンナップを破いたらしいんですよ。そしたら、その子がウワーッと泣いて、さあカメラを回せって。そんな感じで撮ることも可能なんですけど、僕たちはそこまでタフではないので、できないわけですね。
僕たちと言っているのは、今回、ふたりで監督したからなんですが、僕たちがなぜそこで泣いてほしかったかと言うと、本当の孤独、辛さを泣くことで表現してほしかったからですね。そうすれば観客は、ああこの子は悲しいんだな、辛いんだなと思って、彼女に共感できる。彼女の内面を理解できる。悲しいという気持ちを映画のなかの人物と観客が共有する。フィクション映画にはそういう構造があります。僕たちはそれをやろうとしたわけですね。彼女はそれを拒絶したわけですが、おそらくプロの大人の俳優だったら、やれと言えばやりますよね。普通は。だから、映画にはだいたい従順な人たちが写っているんです。これは余談ですけど、大抵の映画には何か言われたら、はい分かりました、と言ってそれをやる人たちが写っている。こんなことやりたくねえよ、と言う人は写っていない。つまり、どんな役柄であれ、そこに写っている人はある従順さを表現している。それは降伏と言ってもよいのかもしれませんが、彼女はそれを拒絶した。役と自分を単純に区別することはできない。つまり、演じれば悲しい気持ちになるから嫌だと彼女は言ったんですね。そのとき、ブレッソンのことを思い出したんです。ブレッソンは「シネマトグラフ覚書」という本を書いていますよね。お読みになった方は多いと思いますけれども、演出の仕事をしている人は結構読んでいるんじゃないかと思います。是枝裕和監督もどこかで言及されていました。あの本には、僕たちがやらせようとした演技は現実であるかのようにみせる物真似、猿芝居のようなものだ、と書いてあるんです。そういう演技を、あの書物は徹底的に否定、攻撃している。それに対してブレッソンが提示するのは「モデル」という概念ですね。彼、彼女たちは感情や何かを理解して、表現しようとしてはいけない。そういう回路を断ち切って、台詞はただそのまま読めと。だから、ブレッソンの映画の俳優たちは、台詞を自分の言葉であるかのようには発話していない。まるで自分が読んでいる言葉を自分で聞いているような演技なんですね。だから、いくらその演技を見ても、彼、彼女の内側で何が起きているのか理解できない。僕たちはブレッソンの映画の画面に釘付けにされるんですが、それを理解することはできないんですね。彼女はそこに立っている。けれども、いったい何を考えているのか、何が起きているのか分からない。僕たちはそのような状況にポンと投げ出されて、だからこそ、ただ見つめるほかなく、画面に釘付けにされるのかもしれません。だから、『ユキとニナ』を撮っていたときに、確かに困ったんですが、でもここで何かを理解させようとか、彼女の内面を僕たちが表現しようと思ってしまうのは間違いなんじゃないかとも同時に思ったんです。分かった、やらなくていい。彼女にそれをやらせることはできない。違う道を発見しよう。それで本当に映画になるのか、これで観客は何を理解するのか不安はありましたけれども、ブレッソンのことを思い出したことで、これで良いのだという確信ももって僕たちは撮影を進めることができたんですね。
これも個人的な話なんですが、イザベル・ヴァンガルデンとか、アンヌ・ヴィアゼムスキーとか、ドミニク・サンダは僕がアテネ・フランセ文化センターに映画を観に通っていた頃のミューズだったんですけれども、驚くべき体験をしたんです。『不完全なふたり』という映画を撮っていたときに、パリの撮影の初日の現場にスチールマンの女性がいたんですよ。宣伝用の写真を撮る人ですね。どこかで見たことがある人だなと思っていたら、彼女から話しかけてきてくれて、私はあなたの『M/OTHER』を観てどうのこうのって感想を言ってくれて、お名前を聞いたら、イザベル・ヴァンガルデンって言うんですよ。あれ? あのイザベル・ヴァンガルデンさんですか? と聞いたら、そうですって。まさかここで『白夜』を見ていた私がイザベル・ヴァンガルデンに写真を撮られることになるなんて、ちょっとビックリしたんですね。『白夜』に出演した彼女はしばらく俳優として『ママと娼婦』とか『ことの次第』とかに出演しましたけれども、後に写真家になるんです。ただ、当時、彼女は不遇で仕事がそんなになく、だから、かつての友だちが仕事を回してあげようと映画のスチールマンに呼んだりしていたんですね。『不完全なふたり』のときは、キャメラマンのキャロリーヌ・シャンプティエが彼女に声をかけたようです。イザベル・ヴァンガルデンは非常に真面目なスチールマンで、撮影が終わると役者を留めてですね、今のをもう一回やってくれと言って、同じ芝居をやらせてバシバシバシッって写真を撮るんですよ。そしたらキャロリーヌが怒りまくりまして、同じ芝居を何度もしたら役者が疲れちゃうからやめなさい、あんた邪魔よ、と言って、イザベル・ヴァンガルデンをクビにしちゃったんです。撮影初日で。さすがに可哀想と思いましたね。イザベル・ヴァンガルデンをクビにしちゃうキャロリーヌは凄いなとも思ったんですけど、現場に呼んだのも彼女ですから仕方ないですね。でも、このままじゃ勿体ないと思って、撮影が終わってから、プロデューサーと一緒に彼女にアパートに行って、カメラを回しながら一、二時間ぐらいインタビューさせてもらったんです。今、その映像は手元にないので、今日お見せできないんですけれども。そのときに色んなことを話して、印象的だったのが『白夜』の撮影の話なんですね。「シネマトグラフ覚書」で提示された「モデル」という概念を知っていましたし、あの映画は彼女のはじめての出演作だったので、ブレッソンに言われるがままだったのかなと思っていたんです。まるで人形のようにね。けれどもヴァンガルデンは、私たちは抵抗の世代だから撮影現場でブレッソンにガンガン抵抗した、と言うんですよ。共演者と抗議したりとか。具体的に何を抗議したのかは聞き出せませんでしたけれども、もの凄く戦ったと言っていましたね。当時、すでにブレッソンはあるステータスを確立していたでしょうから、そのブレッソンに若い出演者たちが異議申し立てをしている図はなかなか素晴らしいなと思って、イメージが変わったんですね。ブレッソンの映画における「モデル」は必ずしも従順な人たちではなかろうと。彼女たちは決して自分たちの内面を表現しませんけれども、でも自分であることをそれぞれのやり方で追及しているんだろうと思うんですね。そのせめぎ合いがあの佇まいに表れているんじゃないか、ブレッソンの映画にはそういう抵抗が反映されているんじゃないかと思っているんです。
『罪の天使たち』に出演しているのは職業俳優で、パンフレットにはブレッソンと俳優たちとの間でかなり葛藤があったと書かれていましたけど、想像に難くないですね。彼女たちがこう表現しよう、この素晴らしい台詞をどう言おうかと考えているときに、そういうことを考えるな、そういうことはやめてくれと言われたら、やっぱり怒りますよ。後のブレッソンの映画に見られるような、素人の俳優たちを使った形式的なスタイルは、この映画では見ることができないのですが、でも、それゆえにブレッソンの映画のあるコアな部分がよりはっきり見えるような気がするんですね。この映画における主人公アンヌ=マリー、そしてテレーズ、このふたりの女性が物語の軸となるわけですけれども、彼女たちは決定的に分断された存在です。片方が愛を与えようとし、片方はそれを拒絶する。和解、あるいは理解しあうことが不可能である。そんなふたりの関係に、最後の最後になって変化が起こるわけですが、それはある行為で示されるのであって、心理的な説明はまったく無いんですね。心理的なドラマとしてではなく、ある瞬間にそれがふっと訪れる。その瞬間を普通の映画の役者であれば一生懸命演じるはずなんですけどね。彼女の内面に起きた変化を演技によってなんとかして表現しようとするはずなんですけど、おそらくブレッソンが徹底的に抑制したんだと思います。ここに僕は映画の結晶のようなものが表れている気がします。心理や意味を越えて、ふっと降りてくるものを写し取る。それは恩寵のようなものだとも思うんですが、最近、恩寵という言葉を聞いたのは、来日したジャック・ドワイヨンが自らの演出の方法について述べたときです。彼は何十回もリハーサルをするんですね。『ポネット』のポネット役の女の子にもやらせているんですよ。信じられないんですけれども。何十回もやらせると、ある瞬間に恩寵が訪れる。神から何かが降りてくる瞬間があるとドワイヨンは言うんですね。それは分かるような気もして、何十回もやって、へとへとになって何をやっているかよく分からなくなったときに降りてくるわけですね。つまり、訳が分かっているというのは、すべてが理解可能な世界であって、それは心理であり、意味である。それが分からなくなった瞬間、ふっと降りてくるものが、映画が体現しうる精神なんじゃないか。ブレッソンの映画とドワイヨンの映画はまったく違うのですが、映画にはそれが訪れる瞬間があって、また、それが可能であるということです。心理や意味を越える何かそういったものに価値を見出すことが非常に難しくなってきている今、この映画がこういう形で上映されて、その瞬間を見ることができたのは非常に刺激的だったと思います。お話できることはこれくらいです。ありがとうございました。