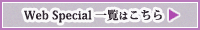トーク「新日本作家主義烈伝vol.12 堀禎一」
2016年6月25日
■寄稿
堀禎一監督が静岡県浜松市の大沢集落の人々と自然を撮った『天竜区奥領家大沢 別所製茶工場』『天竜区旧水窪町 祇園の日、大沢釜下ノ滝』『天竜区奥領家大沢 夏』『天竜区奥領家大沢 冬』は、この地に働く人々のいくつかの肉声を除けば、堀監督自身による素晴しい画面と音と編集によるソロ・ワークの傑作である。インタビュー中の発言のとおり、それまで劇映画のフィールドで活躍してきた監督ご本人はあくまでも集団作業こそが映画との立場だったが、音楽の分野ならソロ・ワークとグループ・ワークの往復が当然ありうるように、またジャン=クロード・ルソーやクラウス・ウィボニーら個人制作のデジタル映像の時代のすぐれたソロ・ワークを追ってきた聞き手としては、『天竜区』シリーズを必見必聴と言わずにはいられない。
赤坂太輔(映画批評家)
■トークゲスト
堀禎一(映画監督)
司会:赤坂太輔(映画批評家)
ーーこの『天竜区』シリーズを撮った場所に行くのはここからどのくらいかかるんですか?
いつも袋井からこの『天竜区』シリーズで制作を一緒にやってくれている、内山丈史くんという自主上映をやっている若い友人と彼の車で、東海道を海の方から秋葉街道沿いに山に上っていきますから・・・水窪の町までは2時間くらい、そこから30分くらい行きますから・・・2時間半くらいですかね。
ーー最初に堀監督からこういう映画を撮るんですよ、とお話を聞いていて、しばらくして送られてきたディスクが『製茶工場』で、まだ粗編の段階でしたか、すごいと思ったと同時にまだ未完成なわけで(その後で)話をしたことを覚えています。昨日初めてスクリーン上で拝見して、その後で夏編を続けて見せてもらうと、時間が経って変わってるなと思ったと同時に『製茶工場』はすごいけれどその場所と人に慣れておらず、手探り的な、こう言っていいかどうか、初々しい感じが伝わってくるんですね。その後夏編を見るとずいぶん洗練された感じが出てきていて、さらに冬編になるともっとダイナミックな感じがあるんです。そういうところに監督自身の被写体に対する態度の変化のプロセスみたいなものが出ているんじゃないかと思うんですが。
よくお気づきになっていただいたと思います。そんなに丁寧に見ていただいてありがとうございます。
ーーいや、ディスクをいただいてから時間があったので何度も見ることができたというだけですが(笑)。
あの、劇映画の助監督やテレビのADだったりしてるので、山の方々とお話しする機会はあったんですよ。ただその時は、企画の条件交渉が多かったんです。その中で普段の生活の話にもなったときに、いつかそういう山の日常の生活も描いてみたい、と思って内山くんと出会って1年くらいロケハンしていたんですよ。その間、カメラを持たずに山を見たり土地の人と話したりしていたんですが、その時本当は怖かったんですね。
ーー怖かった?
あまりにも自分が山の生活を知らなかったんで。
ーー自分の作品じゃなくて、他人の番組や作品の助手だったときは?
その時は怖くないです。やることは決まってるんで。その劇に合うような場所を見つけて、その小屋なら小屋、工場なら工場をお借りして撮影させて下さい、役者が入ってこうなります、とか。またはダムで水没した村の歴史を辿ります、というならやることは決まっているんですよ。
ーー(今回)自分の企画だったから。
企画意図がなかったんですよ(笑)。要するに自分で何を撮ったらいいのかわからないけど、その場所に惹かれて何回も何回も通っていて。内山くんは帰りの車で「コレ本当に何かやるんですか?」って何回も聞いてましたからね。1年くらい。
ーー 撮り始めるまでに1年くらい時間がかかったと。
かかりましたね。
ーーじゃそのあいだはずっと・・・
そこに行っていただけですね。
ーーそこから『製茶工場』に入って・・・今回4本の上映作品があって、『製茶工場』は工場の映画、『祇園の日』は畑での農業の映画、で『夏』、『冬』はそれぞれの季節の日常の生活や時間が収められた映画で、冬は特に実りがあるわけじゃないですか。だからそこの部分に加えて自然があって、歴史を語ってくるというふうに、非常にダイナミックに発展してくるじゃないですか。そこに滞在するにつれて監督ご自身も深い部分に到達することができるようになってきた、そのプロセスも定着されているように思います。
ありがとうございます。僕の方から言わせていただくと、あまり僕が何回も来るので、この場所の方々が、あきらめて下さったというか(笑)あまりにも何も知らないので、教えてやらないとどうしようもない、と思って下さったと思うんですよね。
ーー別所さん御夫妻の声が入っているじゃないですか。あれはしゃべってください的なインタビューではなく、何となく話しているところを録っているわけですか。
いや、そうなんです。こういう話を聞きたいなと思って行ってるときもあるんですけど、「寄ってけ」「上がってけ」という言葉を使うんですが、メシを食って行け、お茶を飲んで行けという意味で、その時「カメラなんか置いて来い」って言われるんですが(笑)そういうわけにもいかないので、でも(カメラを持ってないと)すぐ忘れちゃうんで、とか言いながら(音も)撮らせてもらっていたものなんですよね。それで、何か聞きたいことがあるんだったら、何でも教えてやろう、と。
ーー最初に製茶工場に被写体を集中して60分の映画になったじゃないですか。それはとりあえずのことだったんですか?
とりあえずというより、画なんですよ。何を撮ったらいいかわからないから、テスト撮影を兼ねて、自分はカメラマンでもないし、自分の作品でカメラを持つっていうのは、徒弟制度で育っているので、大変よろしくないことなんですよね。映画は共同作業が基本なんで。まあそれでも自分がやろうっていうことで最初に撮ってたのは石です。石。次が水になって、次に空になって、山になって、木になって、虫になって、ジョンっていう犬になって、人です。製茶を撮り始めたのは、ある時行った時に、高地なんで痩せているから、牧ノ原のような低地みたいに何回もお茶が穫れる場所ではないんですが、やはり霧がかかる低温のところは上手にやればとても美味しいお茶が穫れるというので、材木が安くなってしまったためにお茶に収入が切り替わって。けっこう高級なお茶なので、そのお茶がなかったらたぶん収入がなくなってしまって村はとっくになくなっていると思うんですが。その村を支えてきたお茶畑が霧に包まれて、雨にだんだん打たれていく、もし昨日御覧になった方がいましたら(そのシーンが)あったと思うんですが、ああいう画を見た時に、これは撮らなきゃいけないな、と。とにかく製茶までをまず撮ろう、と。で、その後は自分が旅行者として来てるわけじゃないですか。なので、自分なりの旅行者としての映画を撮りたい、というので祇園というのがあるのは知っていたものですから。子供たちにも怪しまれるじゃないですか(笑)このお兄さんたちは何やってるんだろみたいなことになるので、(『祇園の日』は)子供たちを撮って早くDVD渡して記録残そうという短編だったんですよね。
ーー『夏』『冬』になるとヴィジョンというか対象がだんだん大きくなっていったというか・・・
そう考えてもらって構わないです。ほとんど杉で埋まってる山ですけど、もともと焼き畑ですから。そういう話を聞いていくうちに、見ている風景というのは人の歴史だということが徐々にわかってくるわけですよね。そこに転がってる岩だったり階段だったり家だったり、対象が大きくなっていったし、村の向かいにある麻布山は、何回も通っているうちに、彼岸の頃になると、まっすぐ山頂から日が昇ってきてるんですよね。ここは木地師という器を作ったり放浪していた人たちが開いた村だという歴史があって、村を開く場所撰びからして暦についての深い知識も持ち合わせた、かなりの技術を持った人たちが開いた村だということがわかってくるんですよね。あの村は八家までしか増やしてはいけないという規則があるんですが、もちろん耕地が狭いから、昔の家族は10人くらいいますから、自給自足で食料を充分に穫れないからっていうのもあります。でも親小作関係がないっていうのも徐々に知っていったんですよ。畑の割り振りであったりというところにそういうことが出ているということは、おっしゃるとおり、被写体が大きくなっていったということでもあるんです。
ーーそれで最初の『別所製茶工場』を見た時に、そういう情報関係はないわけですよね。ひたすらそこにいる方たちと、風景、自然といったものがあるわけじゃないですか。普通にドキュメンタリーっていうようなものを見ると・・・たいがいドキュメンタリーを見に来る人は、情報を見に来るっていう人がほとんどだったりするわけじゃないですか。まあテレビの非常に悪い影響だと思うんですが、文字情報が先に来てしまうような現在の環境の中でこの映画を見ると、それは全くないわけです。後の『夏』『冬』編になると別所さん御夫妻の語りが入ってきますけど、訛っておられますから、(東京の)私たちが聞いていて決してわかりやすくはなかったり・・というかよくわからないところもありますけど(笑)、特に「情報的なもの」は撮らないようにしよう、入れないようにしようとか考えましたか?
まず訛りではなく、うるわしい「古語」と呼んで頂きたいですね。(笑)それはともあれ、それはわざと情報批判という考え方をしたんじゃなくて、まあ僕もテレビをやってますから、そういうものも映像の力としてすごいですからね。それをないがしろにするつもりはないんですが、あの、聞かないようにはしてました。『製茶工場』のときも、いったんカメラを向けるんだから、その人たちから教えてもらったことを後で勉強したりしましたけど。その話が出るまでは、疑問に思っても聞かないっていう。ただ不思議なのは、『製茶工場』は、昨日御覧になってない方もいらっしゃるので恐縮ですが、確かに、製茶の方法だとかを全く知らないで撮ってるんです。でも、あのお茶摘みの方の中で、自分は知らなかったんですよ、でも通いで農作業にいらっしゃる方もいて・・・ちょうどあの時期は農繁期になってくる頃で、普段は町に住んでいらっしゃる方で通いで山の畑に来られる方の顔は知らなかったんです。ところが知らないで撮っていても、お茶摘みをしている方たちの寄り(画面)がある男の方と女の方、その方たちだけが村に住んでいらっしゃる方たちなんです。だから、よく画だけで考えると言っても、なんかこう、記号みたいになっていて、たぶん歩き方とか、採り方とか、そういうことだと思うんですけど。別に情報がなくても、この人は寄っておかなきゃいけないと思った方だけが村の方だったという。案外言葉になっていなくてもわかるのかなあっていうふうに思うことが多かったですけどね。
ーーそういう情報がなくても、自分が観客として見ていると、例えば農業用のモノレールがダーッと出てきて、向こう側に去って行く時に、次の画面でつながって追っていってくれるじゃないですか。ああいうのってすごく嬉しいんですよ。あるいは『夏』編だったと思いますが、おばあちゃんが草を背負ってどこかに去って行く、そこを(固定画面をつないで)追ってくれるというのは嬉しいんですよ。そこで脈絡ない山とか自然とか川とかっていうそれはそれで一画面一画面すごいなって思ってるんだけど、そこで続き物というか物語を見出す、みたいな。そういうのが非常に嬉しいんですよね。
それはやっぱり劇映画の先輩たちから学んできた方法ですから。いや、走るんですよね。走ってモノレール追いかけるとか。なんていうか、表を撮ったら、切り返しも撮りたくなるんですよ。なので、走って・・・がんばる(笑)。
ーー具体的に何か思い浮かべた映画があるんですか?
モノレールのところは、バカな話していいですか?(笑)ドン・シーゲル監督の・・シャーリー・マクレーンがヤギかロバかなんかに乗っかって、クリント・イーストウッドが・・・
ーー『真昼の死闘』ですか。
永井さんていう別所さんのお隣の方が乗っていらっしゃるんですが、あの方がイーストウッドに見えてですね(笑)それでその映画を思い出しました。これは引きだ!なんて。そんなアホなことを思いながら撮ってはいました。
ーーその時、堀監督がすごいな、と思うのは引きで撮れるっていうことです。それが自然だっていう感じで撮ってつなげられるというのは偉いなっていう。寄るよりは引くってなるのは、システムの中で育ったという・・・
そうでしょうね。先輩たちから教えてもらったんでしょうね。
ーーあと、クロノロジカルにシリーズとして見ていくと、最後の方にいくにつれて、寄ったり引いたりがすごく激しくなる。さっきも言いましたけど、冬編ていうのは実りがあるわけじゃないですか。収穫物があって、食べるっていうことにつながっていく。そして次の年のために種をまくっていうことで、寄ったり引いたりっていうことになるんじゃないかと思うんですけども。それ以上に動いている感じがするんですよね。最初の映画に比べると。最初の映画はもちろん作業を撮っているわけだから人は動いているんですけど、最後の4本目になると、人は動いてないんだけれども、固定画面だから動いてないけれどもダイナミックな感じがあって。それは自然にそうなったんですかね。
それは自然に、撮りたいものがあるわけですよね。地元の方々が作っているだんごがあって、きれいじゃないですか、美味しそうですよね。『祇園の日』のほうで、あのおばあちゃんは亡くなっちゃったんですけど、柿の皮を干して、小豆を使って柿餅(かきもち)という餅にするんですけど、あれホントにきれいなんですよね。それは撮りたいものを撮っていくっていうのがあるので・・・また適当なこと言いますけど、そういう方法で映画なんか出来るのかな?と思ったんですよ。要するに、冬に入るとお話もそんなにない、農作業も冬に入ると全くない、風景と、食べ物と、なんていうかそういうものしかなくて、所謂「死んではいないけど、止まっている」んですよ。鳥もそんなに鳴かなくなった、虫も飛ばない、そういう中で撮って映画になるのかなって思ってまして。
ーー限界へのチャレンジみたいな?
いやそんな格好のいいもんじゃなくて、一つ思ったのは、ええとですね、これは別に比べてることは全くないですよ、全くないですけど・・・小津監督って、実景つないでるよねって思い出したんですよ。止まってる実景をね。自分の撮りたい画を撮ってつないでいらっしゃる。僕は通常言語の他に、通常言語に還元できない画面の言葉、つまり映像言語というものが実在していると考えているんですね。たとえば『晩春』という映画があって、そうですね、わかりいいとこだと、有名な壷の画面と言われてるものがありますよね。あの壷の画面が入って、何につながるのかと思ったら、シーン替わりの龍安寺の引きじゃなくて、龍安寺の石庭の画面につながるんですよね。だから、ああいうことを、恐れ多くもやってみようと。画でつながるんだったら、壺の画面の形と龍安寺の石庭の画面の形があれだけダイナミックに跳ぶんだったら、僕も百分の一か千分の一かそのぐらいの感じでやってみた、と。
ーー逆に言うと限界に来たので出したみたいな?
だから考えついたわけじゃないですから(笑)何というか苦し紛れで何かこうつないだら、普通全部切らなきゃいけないようなカットだったんで、このフィックスでつなぐようなことを何回も何回もやっていたら、あっそう言えば、あったよねって思い出したんです。
ーー特に『冬』の後半は引いたり寄ったりになってくるんですが、物とか、土とか、山とか、引いたり寄ったりが、引いたり寄ったりに見えないというか、それ自体が引いたカット寄ったカットじゃない「一つのカット」に見えてくるというか。ちょっとNOBODYの田中竜輔さんがウェブ上にこの『天竜区』について書かれていて、すごく面白かったのは「一つのカット自体が一つの宇宙を形成している」みたいなことを書かれていて、宇宙っていうと一つのイメージを想像しちゃうんですけど、今言ってるのは、引いたり寄ったりする同じ土とか山とかが、引いたり寄ったりじゃない別の何かになるということが面白かったんですね。
それは難しいんですが・・・まあそんな難しいことを考えているわけじゃなくて、撮りたい画を撮っているだけなんですが、そこで思いつくのは、植物、野菜なんですよね、当たり前なんですが、畑に植わっているものって食べ物なんですよ。だから根菜を撮るときは、根の方を撮る。何というか、それが引きで、畑を撮って、じゃがいもとかあるじゃないですか、土地の言葉でじゃがいもを「じゃがた」と言って、大沢の「じゃがた」は在来種で
水窪全体の特産品でもあるんですが、500年前に入ってきて痩せた土地で育ちやすい作物があっという間に山の方まで伝播したんでしょうけど、他の物と混ぜないで作ってるんですけど、根菜はやっぱり土を撮らないと、感じないじゃないですか。(映画を)見て下さる方の想像力を喚起できないじゃないですか。そういうことだと思うんですよね。実がなる物は実を撮る。根菜の方に向けるから土を撮るということなんじゃないかと(笑)山も、別所さんにお話しいただいてますけど、引いてるときは、まあきれいで、魅入られているような感じですよね。そのうち信仰の対象だっていうのがわかったんですけど、上の方だけ撮ると、また雰囲気が変わるじゃないですか。向こうから風が吹いてくるんで、風の音に合わせて細部が変わるじゃないですか。見え方が変わるじゃないですか。麻布山というのは風の神様とされていて、大沢の向かいの大寄(おおより)という集落には「風の三郎神社」という神様が祀られている位なんですが、地元の方は面白いこと言うんですけど、山の頂上のことを峠って言うんですよ。足で歩いてるんで。峠を越える時に、あっちから吹いてくる匂いとこっちから吹いてくる匂いが全然違うって言うんですよ。で、お嫁さんに来た人は、自分の実家に帰る時に、峠に立つと、在所の風が吹く(笑)と。風の音とか流れっていうのは、あそこまで急峻だと、ハッキリ違うんでしょうね。
ーー雲とか霧とかが山を覆っていくリズムとかがカットのリズムを決定してたりするんですかね。
あれ不思議な話があって、まあまた適当なこと言いますけど、『冬』の時は、撮ってる画のリズムを作っていったんですよ。まず画を切っていって、つないでいった。で、インタビューというか、別所さんにお話ししていただいている音っていうのは、これはまた別個に作ったんですよ。昨日見ていただいたのは恣意的に短くしたり長くしたりしてるところがあるんですけど、この『冬』っていうのは、自分なりに感じた土地のリズムで切っていったんですよ。で、音を当てていったんですが、2コマとズレたことないですよ。だから僕は風土論とか別に皆さんにお薦めするつもりはないですけど、何かこう、霧もそうかもしれませんし、動きのリズムっていうと、人が生きているリズムと自然のリズムっていうのは、何かあの、ズレなかったですね。今回。
ーー今回劇映画も上映されましたけど、劇映画の場合、スタッフさんや役者さん、いろんな人たちがいるなかで作られたわけじゃないですか。この天竜区シリーズの場合、制作は内山くんと、ほとんど二人なんですか?
二人ですね。
ーーあと自然とかじゃないですか。猿とか鹿とか犬とか。それは今回やっていてどうでしたか?
僕はだから映画っていうのは共同作業で、それぞれの領分があると。演出部は演出、役者さんは役者、撮影は撮影、照明は照明、音声は音声、編集は編集っていうように、それぞれのパートにしかわからない世界があって。その隙間っていうかあわいでできあがってくるものが映画だっていうふうにずっと思ってきてますから。まあ邪道は邪道なんでしょうね。
ーー自分の撮りたいものを撮るっていうことで、それまでの劇映画を撮っていた時以上に動かなきゃいけなかったのか、それとも・・・
それは今回脚本がなかったことが大きいかもしれませんね。脚本に則らなくてよかったというのは大きいかも知れないです。少ない人数でやってると。動物に関しては、ほぼ事故みたいなものですね。皆さん何でこんなことやってるのかと思ったかもしれませんが、三脚に乗っけてフィックスで撮るとだいたい動物って逃げていくんですよ。三脚出してカメラを構えるうちに逃げていく。で三脚置いて撮れない動物は撮らないっていう方針で(笑)構成台本で「猿が出る」てあったら必死で撮りに行くんですが、それがなかったのが大きいかもしれません。
ーーあれはたまたま写ってしまった猿なんですか。
あれはたまたまボス猿で、なかなか度胸があって、三脚据えてても大丈夫だったと。鹿もそうですけどね。
ーージョンはどうなんですか。
ジョンはですね、あれはちょっと天才というか、人の命も救ったこともあるんですが、御覧になった方が「何だこの映画は風景ばっかりで」なんて思ってるとジョンが出てきたりして、あれは映画のツボを心得た犬でして、「何か欲しいんだよね」っていうときにやってくれるんですよ。
ーーそれはリクエストなしに?
それはできなかったですけどね。
ーー慣れているような犬じゃないですか?
いや、最近慣れてますけど柴ですからえげつないですよ(笑)内山くんは子分と思われて、内山くんがいるだけでワンワン吠えるんですよ。アレだって猪とかに吠えてるんですよ。畑に入ってくるのを追っ払って。今日見ていただいたのに夜明けのシーンがあるんですよ。あれでワンワン吠えているのは、僕のことをカモシカか何かと間違えているんですよ。あんな早い時間にあんな影が動くわけはないってことで。ちなみにカモシカって、見た目がどこぞのおっさんか、みたいな感じなんですよ。(笑)ずんぐりしてて、短足で。ですから、男性が女性の容姿を褒める時に、カモシカの実体を知らないで、「きみはカモシカのように美しいね」なんて言ったら殴られても仕方ないですよ。(笑)ともあれ、ジョンはすごいんですよ。あれは大した・・・でもそれは、変な話ですけどジャン=クロード・ルソー監督と京都で会った時に、『De Son Appartement』っていういい映画があるんですけど、そこでルソー監督が飼ってらっしゃる猫がすごいいい演技するんですよ。で、「何で彼はあんなにうまいんだ」って聞いたらルソー監督も「彼は映画を知ってる」って言ってました(笑)。お一人で撮っておられて非常に刺激を受けた監督です。
ーー『天竜区』のシリーズはこの後があるんですか?
ややこしいところに入っています。今日見ていただいたもので一周なんですよ。その後大変なことを聞いてしまって、地元の方にとっては実際にあったことだから、別に大変でもなんでもなく、ごくごく当たり前のことなんですが、僕にとっては衝撃だったものですから、どうやって撮ろうかと。
ーー他は、劇映画の方は?
今は検討していただいているところなんですが、こうやって光栄にも特集を組んでいただいて、一周したところで初心にかえって、古巣に戻るというより、あらためてまったく新しい気持ちで映画に、先輩たちから身をもって教えていただいたピンク映画の心意気を、それはすべてのジャンル映画の精神同様、映画の魂そのものでもあるんだとぼくは強く思ってますが、受け継ぎ生かせる題材に思いっ切り挑戦してみたいな、と。