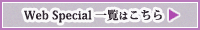講演
「偉人たちとの冬――映画の比較シリーズ『リンカーン大統領を比較する』」
1989年2月25日
石坂健治(映画研究者)
昨日は重苦しく退屈な一日でしたが、私はそんなこととは無関係に入試を実施していた新宿区のW大学の関係者なので、試験監督をしていました。それで、10時15分頃から新宿御苑で弔砲が30秒間隔で21発鳴らされることを試験の前に受験生に伝えろというお達しがありまして、そのことを教室で知らせたら、彼らがかなりビビッてしまったんですね。言わなきゃ良かったって思いました。この通達文というのが馬鹿な書き方をしていて、「亡き昭和天皇の……」といった書き出しなんですね。この「亡き昭和天皇の……」というのを聞いた瞬間にパッと受験生たちが姿勢を正したんです。あ、今日はヘンリー・フォンダの姿勢についてもお話ししたいと思っているんですが、それはともかく、この反応から察するに彼らはこれに関して何かさせられるんじゃないかと思ったのかもしれません。実際、どこかの大学は黙祷したそうです。W大学ではそういうことはしませんでしたが、試験会場は戸山町で新宿御苑からあまり離れておらず、弔砲の音がやかましいだろうと予想してこの通達を読んだんです。それで、実際どうだっかと言うと、まったく何も聞こえませんでした。音というのはそんなに遠くまで届かないようですね。その通達を読み上げたときに、受験生の何人かはちり紙を丸めて耳に突っ込んだりしていたので、気の毒だったなあと思っています。
さて、今日のテーマなんですが、別に天皇の行事の翌日であることを意識して、大統領映画に決めたわけではありません。当初は違う企画を私は希望していまして、いろいろあった結果、グリフィスとフォードという、映画の王道をいく二本立てになりました。当初の企画は、リンカーンは最初から考えていたのですが、もうひとりはレーニンで、「リンカーン対レーニン」でした。リンカーン映画とレーニン映画を一本ずつ上映して何かを考えてみようという試みです。今、各国の首相、大統領クラスがいっぱい来日しているので、東西の友好に役立つ企画と思われてCNN辺りが報道してくれないだろうか、なんて馬鹿なことを一瞬考えたんですね。これは上映フィルムや諸々の都合で実現しませんでしたが、そのときに「偉人たちとの冬」というこれまた馬鹿な企画名を考えて、この「偉人たち」とはリンカーンとレーニンを指していたのですが、結果的に『世界の英雄』と『若き日のリンカーン』というリンカーン二本立てになった。でも、この二本の映画は、リンカーンを演じている役者も違うし、監督も違うので、まあ「偉人たち」と複数で良いかと思って、そのまま今回のタイトルにしました。まあ、レーニンとリンカーンだとテーマが大きすぎるので、実現しなくて良かったかなと今は思っています。レーニン映画についても後で言及するかもしれませんが、まずはこの二本のリンカーン映画について考えてみたいと思います。
去年の6月にここで講演させていただいたときはアルドリッチについて喋りました。50年代ハリウッド映画作家のなかで誰が一番好きかと聞かれて、私はアルドリッチを選んだわけです。大体、50年代好きはニコラス・レイかアンソニー・マンに行き着くらしいのですが、私の贔屓はアルドリッチで、アルドリッチの映画を「ボクシング的世界」と「プロレス的世界」から論じたわけです。50年代映画の翳りだとか暗さだとかと言われますけれども、それはボクシング的であって、一試合にすべてを賭けて、コンディションを研ぎすまして、激しく打ち合って、パッと散るという感じ。一方、アルドリッチが80年代まで生き延びたのは他の作家たちと違っていたわけで、その違いはプロレス的な世界観から解明できるのではないかと思ったんですね。つまり、プロレスというのは年間に二百数十試合をこなして、試合イコール練習のような世界です。ボクシングとプロレスは似たようなリングで行われながらも、まったく対照的なスポーツである。一試合だけ取り上げてみればボクシングはストイックで美しいかもしれないけど、人生とか長いスパンで考えたときプロレス的世界もまた魅力的な表現たりえているのではないか。そういう話をしたら、いろいろと反響がありまして、ある人からボクシングとプロレスは、能と歌舞伎の関係になるんじゃないかと言われました。私はその手のことに詳しくないので少し調べてみましたところ、能というのは伝統があって、ボクシング的な、一期一会、ひとつの舞台に賭ける要素が強いようです。ひたすら個人技を磨き、アンサンブルはほんのわずかで、非常に舞台が緊迫している。それに対して、歌舞伎はまさに本番イコール稽古であるような世界だと。そのように、ボクシングとプロレスの対比が能と歌舞伎にもあてはまるという発見があったのですが、プロレスラーにグレート・カブキという人がいて、この人は言わば文化を横断して存在しています。彼こそまさに「インターテクスチュアリティ」「間テクスト性」ではないだろうかと口走りましたら、友だちから「たけし軍団にはグレート義太夫という人がいるが、義太夫節はどう位置づけられるのだ」と問われ、私は言葉を失い、今もそのことについて考えている次第です。
今までの話はプロローグ兼前回の反省ですが、映画というのは文化現象としていろいろな領域に広がってゆくものだと思っていますので、今後もボクシングとプロレス、このふたつの世界観については考えていきたいと思っています。と言いながらも、すみません、もう少しプロローグを続けますが、ボクシングとプロレスを繋ぐものとして大相撲があると考えています。下位の力士は七勝八敗か八勝七敗で勝ち越しか否かというプロレス的世界なんですが、上の位になるにしたがって、全勝かどうかというボクシング的世界になっていくわけです。ここ二十年ぐらいの統計によると、七勝七敗の力士は八割五分ぐらいの確率で最後の一番に勝つそうです。それを知って八百長だなんて思う人もいるかもしれませんが、私なんかは、これはなかなか大変なことだなんて思っています。この八勝七敗勝ち越し名人のひとりに天龍という力士がいました。ご承知のように、この天龍は今、プロレス界において一、二を争う存在となっています。やはりなかなか凄い人で、新入幕の成績が八勝七敗、そして、プロレスに転向する前の最後の場所も八勝七敗で締めくくっています。僕はこの天龍、はじめは長野の人かと思っていました。天竜川がありますから。ところが、調べてみたら、実際は福井県出身、本名は嶋田源一郎さん。なぜ天龍の名前にしたのかは分かりませんが、相撲の古い記録を見てみましたら、昭和のはじめに天竜三郎という力士がいたそうで、この人は待遇改善を求めて相撲協会に反乱を起こし、自ら新しい相撲協会を立ち上げて興行をやったらしい。こういう大相撲の汚点であるような史実はあまり資料が残されていなくて、この事件に関しても謎が多いんですね。ところで、プロレスと大相撲とに共通する要素として、巡業という制度があります。地方をまわって、必ずその土地の力士が勝つ。おらが国の力士が勝つ。地方で強いのは巡業、自民党、キリンビールと言われていまして、いくらアサヒスーパードライが東京で頑張ってもキリンビールの優位はびくともしない。これはなかなか興味深い問題で、これもひとつ追究していきたいと思っています。
ごめんなさい。そんな感じで映画から着実に遠ざかってきていますが、前置きが長くなってしまいました。さて、今日はリンカーンの伝記映画と言われる二本の作品についてお話しします。一本はグリフィスが1930年に撮った『世界の英雄』、もう一本はジョン・フォードが『駅馬車』と同じ1939年に撮った『若き日のリンカーン』です。30年代のはじまりと終わりに作られた二本の映画です。映画史において激動の時代であった1930年代のはじまりと終わりに作られたこの二本の映画は、さまざまな意味でかなり異なっています。『世界の英雄』はグリフィスの最晩年の作品です。この後、もう一本ぐらい撮って引退している。一方、ジョン・フォードは同じ1939年に『駅馬車』がありますし、その後は『怒りの葡萄』があり、『わが谷は緑なりき』があり、『荒野の決闘』があるわけで、監督としてギンギンの上り坂の時期ですね。この二本は、ある意味でピークを過ぎた監督と上り坂にいる監督の作品とも言えます。そこから、グリフィス論、フォード論を展開することもできるかもしれませんが、今日はその方向ではなく、リンカーン映画論として考えてみたいと思います。
なぜ30年代が激動かと申しますと、トーキーが映画界を席巻したからですね。既に20年代に『ジャズ・シンガー』という映画が作られていますが、トーキー映画があまねく行き渡るのは30年代です。日本でもそうです。そのことを考えてみますと、『世界の英雄』にはほとんど伴奏音楽がありません。『若き日のリンカーン』はほぼ全編にわたって音楽が鳴っています。この差ですね。これは単に伴奏音楽の有無ではなくて、映画作りの思想に関わる大きな問題だと思います。映画が音を持つとはどういうことか。サイレント映画時代も映画館では音がよく鳴っていました。ピアニストや楽団が館内で画面に合った音楽を演奏していたからで、無音のままの上映はあまりなかった。ところが、フィルムそのものに音が記録されるようになって、何が起こったか。台詞が映画に氾濫するようになったんです。音楽は別に目新しくない。以前からスクリーンの外で伴奏をつける習慣があったわけですから。そうではないものを求めて、皆が競って台詞に頼る映画を作るようになったんです。
もうひとつ指摘しておきたいのは、この時期の作品は、トーキーではあるけれども、形式的にはあるエアポケットに入っているということです。今は伴奏音楽、劇伴は娯楽映画に普通に使用されていますが、トーキー初期の作品ではあまり伴奏音楽が使われず、画面のなかで実際に鳴っている音だけが聞こえるように作られている。伴奏音楽とは、その音楽の出所が画面に映っていない音楽ですね。何もない画面から音楽が聞こえてきて、カメラがパンするとその出所が分かる、なんて演出もありますが、本当の伴奏音楽とは画面に映っている物とは無関係に響いている、流れている音楽のことです。実際の音と伴奏音楽の間には、もの凄い発想の飛躍があると思うんです。一昨年に「ウォルシュとその時代」という特集がフィルムセンターであり、サイレントからトーキーになったぐらいの時期のアメリカ映画をたくさん上映したので通っていたんです。音が導入されて、作り手たちが最初に試みたのは、やはり現実音をどううまく使うかということでした。伴奏音楽の目立った使用はほとんどない。『ハレルヤ』という黒人だけが出演している有名なミュージカル映画がありますが、あれも音楽が画面のなかにある。『巴里のアメリカ人』のように、突然、ストーリーがストップして歌と踊りの夢のような時間になることはありません。ウォルシュもトーキー初期は出所が分からない音楽を使うことに非常に弱気でした。ほんの少し使うとか、全然使わないとか、最初と終わりのクレジット画面にだけ使うとか、そんな感じです。グリフィスの『世界の英雄』は、そういう伴奏音楽以前の映画ですね。確かに音楽はあります。けれども、画面、物語のなかで実際に演奏されている音楽が聞こえてくるだけで、伴奏音楽はない。この『世界の英雄』はグリフィス自身が編集した作品ではありません。映画会社や他の編集者によって編集されてしまったため、グリフィスは大変怒ったという話が伝わっています。確かに、グリフィス得意の「最後の瞬間の救出」とはならない。まあ、史実は暗殺されるわけですから、救出が成り立つはずはないのですが。また、南北戦争のシーンは、銃後で憂いているリンカーンの姿が合間合間に挿入されるため、分断された印象があります。あれもあまりグリフィス的な編集ではないですね。音の問題に戻りますと、リンカーンはそんなにベラベラと喋る人ではなかったようです。『若き日のリンカーン』でもそうなんですけど、リンカーンは寡黙なわけです。寡黙な上に伴奏音楽が無いと沈黙がかなり目立つ。その点に関してもフォードはうまいですね。『若き日のリンカーン』では弦楽器の柔らかいバラードが流れていて、リンカーンの沈黙があまり気にならない。
ところで、音楽について一言だけお話しますと、レーニンを描いた映画とか、ヒトラーを扱った映画なんかもそうですが、伝記映画でよく使われる音楽で特に目立つジャンルは行進曲ですね。二拍子のマーチ。一、二、一、二と確かに単純に勇ましくて分かりやすいのですが、一方で、思考をストップさせると言うか、頭を空っぽにさせて熱狂させるところがある。戦争の時代になると、ナチスのときは特にそうだったようですが、国中が二拍子のマーチの氾濫になる。日本もそうだったようだし、他の国でもそうでしょう。『若き日のリンカーン』でもリパブリック讃歌がうまく使われています。ある人物を輝かせる伝記映画というジャンルにおいては、マーチの使い方が重要である。その点は考えてみる価値があると思っています。
このように、この二本のリンカーン映画を見比べると、音の問題が浮かび上がってきます。そして、今日のメインテーマとしてもうひとつ考えたいのは、リンカーンの姿勢についてです。姿勢と言っても、政治の方針や将来のヴィジョンではなくて、ごく普通の意味での姿勢です。立ったり座ったりしている姿ですね。それについて考えてみたいと思っています。『若き日のリンカーン』について言いますと、こんなに姿勢の悪いリンカーンは他で見たことがない。グリフィスの『世界の英雄』でもリンカーンは椅子に浅く座って、脚を組んで、崩れたような姿勢で映っていましたが、ただ、グリフィスはそれを演出で特に強調していたようには思いません。まあ、『世界の英雄』はリンカーンの一生、生まれてから死ぬまでを描いているので、歳をとって姿勢が多少崩れてくるのは当然です。ところが、『若き日のリンカーン』の方は、『Young Mr. Lincoln』という原題が示すとおりリンカーンの青年時代をピックアップしているのですが、それにも関わらず姿勢が悪いんです。
ちょっと話がズレますが、伝記には、ある人物の全生涯を描くか、一時期の印象的な事柄を描くか、という対照的なアプローチがありますね。全生涯を描く『世界の英雄』と、青年期だけを取り上げた『若き日のリンカーン』。今日お話している二本のリンカーン映画はアプローチのタイプがまったく異なります。このことから僕が連想するのは豊臣秀吉を扱った二冊の本です。吉川英治の「新書太閤記」が秀吉の生涯を描いたのに対し、司馬遼太郎の「新史太閤記」は秀吉が大阪城に入るまでの青年時代を描いています。その後については辞世の句が一句書かれているだけで、それ以外何も触れていない。大変な権力者になったり、朝鮮を攻めたりしたことが書かれていない。それは司馬遼太郎の秀吉に対する考えを図らずも示していると思います。リンカーン映画の方はどうかと言いますと、『世界の英雄』は狙撃されて銅像が映って終わるのに対し、『若き日のリンカーン』は青年時代だけを描いている。これは、プロデューサーや脚本家、フォードらが暗殺の映画化を好まなかったからではないかと思えます。それから、青年期はやはり青春として美しく描けるということもあると思います。
その『若き日のリンカーン』では、『世界の英雄』など問題にならないぐらい、リンカーンの姿勢の悪さが強調されています。おそらくリンカーン本人がそうだったのでしょう。1939年はアメリカでリンカーン・ブームが起こっていて、カール・サンドバーグという人の長大なリンカーンの伝記が出版されてピューリッツァー賞を受賞したり、ロバート・シャーウッドの「イリノイのリンカーン」という戯曲が大変な評判を得ていました。この「イリノイのリンカーン」はRKOが1940年に映画化しています。邦題は『エイブ・リンカーン』。監督はジョン・クロムウェル、リンカーンを演じたのはレイモンド・マッセイという俳優です。この戯曲は各映画会社で奪い合いになったようですが、結局RKOが映画化権を獲得しました。当時のフォックスの社長ザナックがそれに対抗して、この『若き日のリンカーン』を企画したとも言われています。
『若き日のリンカーン』制作の事情はこんなところですが、そんなことは本を読めば書いてあるわけで、問題はこのリンカーンの姿勢です。椅子に浅く腰かけ、脚を組み、ときにはその脚がこんなに上の方にある。どう見ても異常な格好。リンカーン本人にそういうクセがあったにせよ、あまりにも変。こういう姿勢ってどこかで見たなと思いまして、思い当たったのがこの写真ですね。グレン・グールド。この人は演奏するとき、普通の演奏者が使わないような低い椅子を用いたと言われていますが、この写真では椅子の脚のこっち側が地についていない。これはバランスをとるのがなかなか大変な姿勢です。浅田彰さんがグールドについて緊張を孕んだバランスなんて書いていましたが、異常な姿勢ということで、私はすぐこの写真を思い浮かべました。もう一枚グールドの写真を持ってきました。やはり、こういう姿勢ですね。1960年ぐらいの写真だそうです。私はこの写真を見たとき、グールドがコンサートの途中に酒を飲んで、それでこのおばさんが怒っていると思ったのですが、調べましたら、これはトロントで行われた公開リハーサルで、その休憩時間にミネラルウォーターを飲んでいる姿だそうです。でも、このおばさんはなぜかやっぱり怒っていますね。ともかく、こういう姿勢です。ヘンリー・フォンダのようにグールドもかなり長身だったわけで、そういう人がこういう腰かけ方をすると、身体が斜め後ろ方向に広がって、こんな感じの特徴的なポーズになる。そして、林忠彦という有名なカメラマンが戦後の作家をたくさん撮っていますが、こちらの写真がそのなかでもよく知られている一枚で、銀座のルパンというバーでの太宰治です。バーのカウンターの高い椅子の上であぐらと言うか、立て膝のようにして座っている。良い写真だと思いますが、これも緊張を孕んだ、危うい姿勢のバランスですね。あと、こちらは太宰の墓前で後追い自殺をした田中英光という作家の写真で、太宰ほど危うい姿勢ではないですが、やはり妙な座り方をしている。私が連想した不安定な姿勢で座っている人たちは、みんな早世ですね。危うい姿勢なのにバランスを保ち、くつろいでいるのは、偉人とか天才と言われる人たちにふさわしい身振りのようにも思います。
姿勢について一点補足すれば、嘉門達夫の「小市民宣言」が、今度「小市民ハンドブック」という本になったんです。どういうことをするのが小市民かという実例が列挙されている。「ショートケーキを端から食べて、倒れると悔しがる小市民」とか。日本には「小市民映画」という伝統がありますが、それは小市民的矛盾を気にしはじめると成り立たないんですね。たとえば、小津安二郎の映画は、おはよう、とか、ありがとう、みたいな言葉で成立する世界ですが、そんなに早い時間でもないのになぜおはようなんだ、とか言いはじめると小市民的日常が崩れてしまうわけです。お世話になっております、という挨拶に、お世話なんぞした覚えはねえ、といちいち律儀に応じていると話が前に進まない。それで、その「小市民ハンドブック」にちゃんと載っているんですね、「椅子でバランスをとっていて後ろに倒れる小市民」というのが。ああ、やっぱりと思いました。小市民が偉人、天才の真似をすると危険である、ということですね。
別に、ヘンリー・フォンダがグールドだ、太宰だと言う気はさらさらありません。単に映画のなかのリンカーンの姿勢に注目するだけでも、いろいろ面白いことが見えてくるということです。『若き日のリンカーン』で、リンカーンが他人に紹介された後、人前で演説するシーン。そのときもヘンリー・フォンダ演じるリンカーンは、紹介されている間、脚を組んだりしてダラーンとしているわけです。この映画の後半は裁判劇なんですが、弁護士であるリンカーンの姿勢はこの映画のなかでも最悪ですね。脚を組んで、つま先はこんなになっていて、ほとんどひっくり返りそうな、弁護士がこんな格好で座っていたらどう考えても心証が悪い、そんな姿勢なんですが、まあ映画というのはその辺は深く考えてはいけないのかもしれない。しかし、だからこそと言うべきか、普段は寝転がったり、姿勢の悪いリンカーンがシャキッと良い姿勢になる、その瞬間が見せ場になるわけです。裁判で劣勢を跳ね返そうと相手の弱点を突いていく。それまで無口でなんだか頼りなかったリンカーンがシャキッと立ち上がって、バーッと言葉で攻撃する。それまでの悪い姿勢を見ているだけに、余計に凛々しい。長身のヘンリー・フォンダは立っているだけで見栄えがしますね。そして、彼のダンスは見る者に大きな快楽を与えます。『若き日のリンカーン』にもダンス・シーンはありますが、最も有名なのは『荒野の決闘』じゃないでしょうか。床屋に行って、オーデコロンをプンプン臭わせて帰ってきて、村祭りのダンスに加わる。うまいダンスではないですね。どちらかと言うと下手なんですけど、美しい。『荒野の決闘』は、大げさでぎこちないステップで注目を浴びる。ヘンリー・フォンダのダンスは本当に画になります。
演出について言えば、ダンスは撮るのが難しいと思うんですね。最近の日本映画にはディスコのシーンがあったりしますが、あれはたくさんの人間がひとつの所に密集しているのに方向性が無くて、撮るのが大変難しいと思います。『若き日のリンカーン』のダンス・シーンでうまいなあと思うのは、他のペアがこっち向きに回っているのに、ヘンリー・フォンダと相手の女優のペアだけが反対向きに回っていることですね。輪のちょっと内側を逆向きに回っている。よく考えたら不自然なんですが、一組だけ逆回りしているダンスが大変美しい。逆回転で思い出したのが、ヒッチコックの『海外特派員』です。何台かある風車のうち、ひとつだけ羽根が逆に回転していて、それによって物語が展開していく。これも不自然と言えば不自然なんですが、映画的にはやはり大変な演出だと思います。この『若き日のリンカーン』の一組だけ逆に回るダンスや、『荒野の決闘』の野外のダンスとか、ヘンリー・フォンダの長身を利用した演出が非常に見事だと思います。
では、この『若き日のリンカーン』を語る上でどうしても見過ごすことができない文献をひとつ紹介して、今日の話を締めくくりたいと思います。「カイエ・デュ・シネマ」というフランスの映画雑誌がありますが、1970年にコレクティブ・クリティック、カイエ・デュ・シネマ同人による集団執筆として「ジョン・フォードの『若き日のリンカーン』」という大変長い文章を掲載したんです。フィルム・スタディを志す人にとっては教科書のような、一度は読んでおくべき文章です。これは『若き日のリンカーン』を取り巻く外的な事情から映画自体の精密な分析に至る、ジルベール・コアン=セアという人の「フィルモロジー 映画哲学」という朝日出版社の本がありますがそのコアン=セア的な言葉で言えば、シネマ的事実とフィルム的事実、その両方にまたがるような作業なんですね。その章立てを見ていきますと、「一九三八年—一九三九年のハリウッド」「フォックスとザナック」「フォードとリンカーン」といった映画の周辺の話からはじまって、フィルムの分析に入ると、「選挙演説」「書物」「自然、法、女性」「お祭り」「殺人」「リンチ」「舞踏会」等々の章が続いていきます。映画の時間軸に沿って論文が展開していく点が特徴的です。マルクスとかフロイトとかの当時の思想をもとに、映画をひとつのテクストとして解読していく試みです。映っているものが次々と意味付けられていく。たとえば、「自然、法、女性」という章を読むと、リンカーンが川辺で寝転がって法律書を読んでいる、それはここで自然と法が結びつけられているのだ、という分析になる。そこにリンカーンが心を寄せているアンという女性がやって来ると、それは自然が女性的であることを示唆していて、リンカーンの知の源泉、ルーツは女性的なものに由来している、となるわけです。こんな感じで、どんどん言葉に置き換えられていく。これを先に読んでその後で映画を見ることは、映画の印象がこの文章にかなり支配されてしまうと思うので、お薦めしません。基本的に映画は自由に考えれば良いのであって、この文章はこういう解読もできるというひとつの例なわけです。しかしながら、その解読を、ここまで徹底的に、かつ情熱を傾けて行っているところが、この文章の凄いところです。
さて、最初に構想した「リンカーン対レーニン」という企画に関して最後に申し上げますと、ついこの間まで吉祥寺で『ポーランドのレーニン』という映画が上映されていました。これははっきり言って良くない映画でした。理由はいくつかあるのですが、そのひとつにこの映画の登場人物には台詞が無い。映画全体をレーニンの一人称の語り、ナレーションが物語っている。汽車の音とかはあるんですが台詞は無くて、すべてをレーニンが思い出として語っているんですね。ナレーションというのも画面のなかに見当たらないものですね。どこから響いているのか分からない人の声。つまり、レーニンの天の声が映画全体を統御している。左翼系の新聞などはこの映画を絶賛していまして、それを読んでもどこが良いのか分からないのですが、レーニンに関してはそういう映画もあります。リンカーン映画というのは、ものの本によると二十本以上あるそうで、先ほど申し上げた『エイブ・リンカーン』などは日本でも公開されています。この作品でリンカーンを演じたレイモンド・マッセイという俳優は、たとえばフランク・キャプラの『毒薬と老嬢』では血も涙も無い殺人鬼を演じています。面白いのは、その『毒薬と老嬢』の殺人鬼は当初ボリス・カーロフが演じる予定だったらしくて、レイモンド・マッセイはメイクや衣装をボリス・カーロフそのまま、彼の形態模写で演じたんですね。ボリス・カーロフからリンカーンまで演じるレイモンド・マッセイはなかなかの俳優だと思いますけれども、ともかくリンカーン映画にはそういった作品もある。レーニン映画もおそらくいっぱいあるんでしょう。
私が一番凄いと思ったレーニン映画は、ジガ・ヴェルトフの作品です。ヴェルトフはレーニン映画をたくさん撮っています。あの素晴らしい『レーニンの三つの歌』とかいろいろありますけれども、私が驚いたのは『キノプラウダ』の21番です。これは『レーニンのキノプラウダ』とも呼ばれていまして、フィルムセンターにも所蔵されていて、時々上映されているようです。この作品はレーニンの葬式の一年後に作られていて、棺に入ったレーニンも映し出されるんですが、何が凄いかと言うと、生前のレーニンが徐々に弱っていくその描き方ですね。脈拍と呼吸数が映し出される。脈拍だの呼吸数だのという報道は、皆さん、去年の後半から嫌というほどテレビで目にしたでしょうが、この『レーニンのキノプラウダ』では、その脈拍と呼吸数がアニメーションの線で表されるんですね。レーニンが弱ってくると線がだんだんなだらかになってくる。そして、遂にはまっすぐに。日本のテレビでこういうことやったところは無かったですね。革命後のソ連でレーニンが死ぬ。そういう偉人が死んだ一年後にこういう表現ができる。厳粛ではあるけど、見ているとどこか可笑しさも感じてしまう。私は一年ほど前に、ヴェルトフが黒パンができるまでを逆回転で見せた、黒パンがライ麦にかえっていく『キノグラース』というとんでもない作品について「イメージフォーラム」に書いたのですが、その『キノグラース』も驚きましたし、『レーニンのキノプラウダ』にもびっくりしました。機械が表示する波形を映し出すならまだ分かるのですが、わざわざアニメーションに作り直していて、しかもそれはそんなに正確なものでもない。単なる波線。つまり視覚的表現としてそういう方法を選んだわけです。これが、私の知るかぎりで、歴史的人物に関する最も過激で面白かった映像表現です。天皇という人が亡くなったことに対する映像による反応は、テレビだと、映しっぱなし、垂れ流しにして、あとは昔の記録映像を放送するぐらいですね。これに対する映像表現、映像によるリアクションで面白いものはないかなと思いまして、8ミリとか16ミリとか個人映画、記録映画のジャンルにはあるかもしれないと予想し、幾つか見てみたんです。記帳に並ぶ人々を撮影して、その映像に個人的なモノローグがボイスオーヴァーするといった作品はありましたが、それだけでは弱い気がいたしました。まだまだ探してみようと思います。こんなところで今日のお話は終わりです。ありがとうございました。