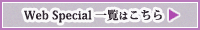講演「映画作家への白紙委任状」
2001年6月5日
万田邦敏(映画作家)
万田です。今日はどうもありがとうございます。小津の『彼岸花』についてお話したいと思います。私が小津安二郎の作品を最初に意識的に観ましたのは、浪人していたときのフィルムセンターの小津特集だったと記憶しています。1974年だと思います。会場は空いていました。その翌年に私は立教大学に入学しまして、蓮實重彦先生の授業を受けたんですけれども、先生はまだその頃、小津に関する文章を発表されていませんでした。当時の小津はイギリスで評価されていたぐらいで、世界的な日本映画監督としては黒澤明、溝口健二の方が主流でしたね。1975年に大学に入って、蓮實先生の授業を受けたときに、最近面白い映画をご覧になった方はいませんか? と先生が質問されましたので、私は浪人時代に観た小津の映画の話をしました。淡々としていて、とても素晴らしい映画だったと思います、と無防備に答えました。そうしましたら、先生が、そうですね、淡々としていますけれども非常に厳しい映画ですね、という風におっしゃいました。当時の小津の映画の一般的な受け取られ方は、淡々としている映画、それだけだったと思います。小津の映画を厳しいと評する映画ジャーナリズムはありませんでしたので、先生の言葉は最初ピンときませんでした。小津の映画を厳しいと評する見方があることが、私には分かりませんでした。その後、二、三年ほど経ってから、先生が小津の映画についての文章をいろいろと発表しはじめます。先生の最初の本が書店に並ぶようにもなったりして、先生が小津を厳しいと言ったことの意味が徐々に分かるようになってきました。その後、さらに二、三年経って、フィルムセンターでもう一度、小津の特集があったんですが、そのときは1974年のときとは比べものにならないほどの盛況でしたね。当時のフィルムセンターの上映は、蓮實先生のお声がかかるとどっと人が集まるような状況になっていたわけですけれども、一時間も二時間も前から並んでいないと会場に入れないような小津のブームがありました。今では誰も小津の作品のことを、ただ淡々としている映画とは言わないと思います。
今日は小津の『彼岸花』の厳しさについてというわけではないんですけれども、ストーリーにおける緻密さについてお話をしたいと思います。小津の映画についてはさまざまな文献がありますので、今日お話することもどこかで誰かがすでに言っていることかもしれません。その際はご勘弁願いたいと思います。実は、今日お話することは一昨年に映画美学校の第二期初等科の生徒にお話ししたことを下敷きにしています。プロットの授業、「プロット入門」ということで『彼岸花』をとりあげました。とりあげる映画は何でも良かったのですが、慣れ親しんでいる映画が授業を一番しやすいということで、この『彼岸花』を選びました。そこで『彼岸花』をビデオで観たりしていたところ、ある発見がありまして、それを授業で話しました。今日もその発見を中心にお話したいと思っています。
この『彼岸花』ですが、僕はもの凄く面白い映画だと思っております。この作品には喜劇映画、ギャグ映画の体裁をとっているところが多々あります。小津の映画には笑えるシーンが必ずある。特にこの『彼岸花』は心底からおかしくて笑える、そういう要素が盛りだくさんの映画になっています。この面白さとは何だろうかと考えました。何がこんなに面白いのだろうかと考えました。もちろん答えはいろいろとあると思います。この映画にはさまざまな人物、面白いキャラクターがたくさん登場する。それらのキャラクターだけでももちろん面白いわけですけれども、いろいろと考えていくうちに、ストーリーが非常に緻密に構成されているということに気がつきました。この映画の面白さの核心に迫る上で、私がどういう手順を踏んで、何を考えついたか、何に思い至ったか。それを今ここで再現したいと思います。
まず物語の構成を考えました。『彼岸花』の物語はだいたい三つのパートに分かれています。最初に「導入部」があります。この「導入部」で何が分かるかと言いますと、佐分利信が演じる平山という主人公に婚期を迎えた娘がいることです。最初に友人の子どもの結婚式のシーンがありますね。その次に「若松」という飲み屋のシーン。この辺りで平山に婚期を迎えた娘がいることが紹介される。その後も平山に婚期を迎えた娘がいることが何度か繰り返し示されます。この「導入部」の最後に事件が起こります。ある日、谷口という青年が平山の会社を訪れ、娘さんを貰いたいと平山に直訴するんですね。平山にとっては大事件です。この事件をきっかけにして、「展開部」がはじまります。谷口が平山の前に現れるのは映画がはじまって40分ぐらい経った頃です。全体が118分の映画ですから、三分の一ですよね。この三分の一が「導入部」になります。
「展開部」は「展開部1」と「展開部2」に分かれます。「展開部1」では笠智衆が演じる三上という平山の友人がいて、その三上の娘がピアニストの男と同棲しているというエピソードがあり、それと平行して、娘と谷口との結婚を認めない平山のエピソードが描かれます。その次にまた事件が起こります。これは映画がはじまってだいたい1時間12分ぐらいのところです。導入部が40分あって、平山が娘の結婚を認めないエピソードが40分弱あって、事件が起こるわけですね。これはこの映画のなかで一番大きいターニングポイントだと思います。山本富士子が演じる幸子が平山にトリックをしかける。そのトリックに平山がまんまとはまる。平山が娘の結婚を許したと勝手に決め込んで、幸子は平山の妻に電話をかける。この事件をきっかけに「展開部2」に移ります。平山が不承不承娘の結婚を認めるという話になります。中村伸郎が演じる河合と平山がゴルフ場のクラブハウスで会って、仲人を頼まれたから式の準備を進めるよ、と言う河合に、ああいいよ、いいよ、と平山がしぶしぶ応じるエピソードもあります。
最後に三番目のパート、「結果」ですね。「導入」があって、「展開」があって、「結果」です。どうやら平山は本心から娘の結婚を認めはじめたようだということで、この映画は終わります。この映画のあらすじを非常に短い言葉で述べるとしたらどうなるか。平山という年配のお父さんに婚期を迎えた娘がいて、その娘の結婚に最初は反対していたけれども、最終的にはその結婚を認めました、ということでしょうか。物語を三つに分けてみて、そういうストーリーだと分かりました。分かったところで面白くも何ともないですね。とすると、この映画はストーリー自体が面白いわけではないということになりますよね。次の段階として、今言ったストーリーを別の角度から考えてみました。娘の思いもよらぬ結婚話に直面して父親が狼狽する物語だと考えてみたわけです。確かにその通りだと思いますけれども、これでもまだ面白くも何ともないですよね。その狼狽ぶりが面白い、じゃあ、その狼狽ぶりとはどのようなものだろうか。さらにもう少し考えてみて、娘の思いもよらない結婚話に直面した父親の話である、ただし父親は頑固だった、そういうことだろうか。その頑固さが面白いということだろうか。これでもまだ自分が『彼岸花』を面白がった、その面白さの核心に達した言葉にはなっていません。『彼岸花』の面白さを人に伝えるときに、今みたいな物語のまとめ方をしても相手はきっと面白がってはくれないだろう。そうすると、ここからさらに考えていかなければいけない。娘の思いもよらない結婚話に直面した父親の話で、しかし父親は頑固だった。この短くまとめた物語に沿って、もう一度この映画の構成を見直してみたらどうだろうか。もう一度、「導入」と「展開」と「結果」に分けて考えてみることにしたわけです。
「導入」——父親は娘にボーイフレンドでもいればむしろ安心と高をくくっている。これは「思いもよらぬ」の前提ですね。この前提が「導入」になっている。「展開」——父親は娘に結婚を約束したボーイフレンドがいることを知って、怒る。その怒る様子がおかしい。「結果」——父親は娘とボーイフレンドの結婚を認める。ここまで絞り込んで、僕のなかでハッと何かが閃きました。この映画がなぜ面白いのか、どういうことでこの映画が面白くなりだすのかが、はじめて少し見えてきたわけです。この男はただ頑固なわけでもない。ただ意地をはっているわけでもない。この平山という男がおかしいのはなぜだ。それはこの平山という男が態度を180度豹変させるからだ。この「態度を180度豹変させる」というキーワードが頭のなかに思い浮かんだときに、この『彼岸花』のストーリー、あるいは平山のキャラクター設定のおかしさが、言葉として多少実感できたような気がしました。そう思って『彼岸花』をもう一度観てみると、田中絹代が演じる奥さんが、あなたは態度をころころ変えるというようなことを実際に平山に言うんですね。平山が結婚式にでないとごねたので、平山の身勝手を責めるわけです。ボーイフレンドでもいれば安心と言っていたのに、いざボーイフレンドができたら反対するなんて無責任だ、180度態度を豹変している、矛盾だらけだ、と言って、田中絹代が演じる奥さんが平山を責めるんです。
ここで話が脱線しますけれども、田中絹代がボーイフレンドを「ボーイーフレンド」と言うんですね。田中絹代の言い回しが微妙におかしい。ちょっと舌足らずなんでしょうかねえ。「ボーイーフレンド」。イが長音になるんですね。ボーイーフレンドでもいれば安心とか言ってたくせに、とか言うわけです。この「ボーイーフレンド」は私の耳にこびりつきましたね。映画には生涯を通じて目にこびりつく画面があるわけですけれども、生涯を通じて耳にこびりつく音というのもあると思います。『彼岸花』で言えば、この「ボーイーフレンド」。これは生涯もう忘れられないだろうなあと思っています。小津の映画でさらに言えば、淡島千景の「ちょいと」とか、『晩春』の原節子の「いーえー」とか、そういった音が耳にこびりついています。ついでにもう一つだけ僕の耳にこびりついている音を言いますと、これは『史上最大の作戦』でして、夜陰に乗じてパラシュートでフランスに落下する部隊だったと思いますけれども、そこの兵士が暗闇のなかで敵、味方を判別するために予めある装置と言いますか、ブリキのおもちゃみたいな物を渡されるんですね。押すとカチッと音がでる。要するに、暗闇のなかでゴソゴソッと物音がして、敵か味方か分からないときに、それをカチッ、カチッと二回鳴らして、相手もカチッ、カチッと鳴らせば味方、鳴らさなければ敵であると。そういう合図を取り決めるんですね。それで、兵士が落下すると、やっぱり暗闇の向こうでガサガサッと音がする。物陰に誰かいるぞということで、連合軍の兵士がすかさずカチッ、カチッと鳴らします。そうしますと、向こうでもカチッ、カチッと音がする。実は、それは敵のドイツ軍の兵士が銃をこうやるその音だったわけですね。それを味方の合図だと誤解した連合軍の兵士が飛び出したところを、ドイツ軍の兵士がバーンと撃つ。それで連合軍の兵士が死んでしまうという悲しい話です。悲しいというのは連合軍にとってですね。ドイツ軍にとってはラッキーです。そのカチッ、カチッが私には忘れられません。これは生涯を通じて耳に残る音でございまして、皆さんにもそういう音がきっとあると思います。映画に関わっていくなら、生涯を通じてこびりつく画面、音は大事になさった方がいいですね、というまったく脱線したお話でした。
話を元に戻しますと、『彼岸花』は180度態度が豹変した男の物語であったわけです。ただ、180度態度が豹変した男の物語、それだけではどうもなさそうだと次に思いました。最初はこの男にとって人ごと、他人ごとだったことが、我がごとになるわけですね。我がごとという言葉があるのかどうかは知りませんが、人ごとに対して我がごとと言っておきます。人ごとが我がごとになって、180度態度を豹変させた男の物語である。そういう認識に辿り着きました。ここまで辿り着いて、『彼岸花』のストーリーの構成をかなり掴んだという手応えがありました。そこで、この認識をもう一度、先ほどの「導入」と「展開」と「結果」に分けて考えてみました。「導入」、これが人ごとにあたります。平山にとってのさまざまな人ごとがエピソードとして綴られていく。最初に中村伸郎が演じる河合の娘の結婚式。これが人ごととして描かれている。次に笠智衆が演じる三上の娘の同棲の話。これも平山にとっては人ごとです。それから浪花千栄子が演じる妙なおばさんの娘の縁談話。これも人ごととして描かれています。よくよく考えてみますと、この映画の冒頭シーンは東京駅の駅員の会話ですけれども、この二人は平山とも他の登場人物ともまるで関係ありませんが、二人もまた人ごととして、人の結婚式をなんだかんだと噂している。あれはダメだとか、今日のなかではあれが一番だったとか、自分とはまったく無関係なことを無責任に話しているところからこの映画がはじまっていたわけです。
次に「展開」があります。今まで人ごとだったことが我がごととなって、平山は態度を180度豹変させ、右往左往することになります。娘の結婚話が谷口の出現によって突如我がごとの問題になる。笠智衆が演じる三上が「導入」で一度、それからこの「展開」でもう一度で登場しますね。「ルナ」というバーに行って、娘の様子を見てきてほしいと平山に頼む。平山はその三上のお願いを「導入」では放ったらかしにしています。人ごととして放ったらかしにしていたんですが、娘の問題が我がごととして立ち上がってきた「展開」では、もう人ごととして放ってはおけず、久我美子が演じる三上の娘を訪問します。平山にとって、三上のお願いは「導入」と「展開」でまるで意味が変わっている。この辺も脚本の緻密さと言いますか、三上は「導入」でも「展開」でも同じように娘の様子を見てきてくれと頼んでいるだけなんですが、その意味がまるで違ってみえる。ちなみに、ここもちょっと脱線しますけれども、三上が最初に映画に登場するシーン、会社の廊下の奥から平山の部屋を目指してトコトコと歩いてくる笠智衆ですけれども、C3POにそっくりです。短いカットです。よく見ておいてください。これも私の目にこびりついたものの一つです。それで、「結果」ですけれども、蒲郡でクラス会がありまして、そこでまた平山と三上が短い会話を交わす。互いに子どものことを話すようになったね、もう歳だね、とか言いながら、三上の言葉には親子の和解の兆しが表れている。それが平山と娘の関係にも反映することになります。
『彼岸花』は、一見おかしなエピソードを緩い構成で羅列した類の映画に見えるんですけれども、今のように考え直してみると、当然と言えば当然ですが、非常に緻密に構成されたストーリー構成になっていて、私はそのことに改めて驚きました。ここまで考えてみて、ハッと膝を叩いて驚いたのは、山本富士子が演じる幸子という女性のトリックの機能の仕方ですね。ただ映画を観ているだけでもあのシーンはおかしいのですけれども、今まで話したことを敷衍してあのシーンの意味を考えてみますと、あの幸子は罠をしかけて、嘘を演じているわけですよね。それを平山はどう思っていたかと言いますと、人ごとと思っているわけです。人ごとと思っているから、あんなおかあちゃんは放っておいてもいいよ、みたいなことが言えるわけですね。その平山の言葉がそのまま我がごととして返ってきて、幸子のトリックが成功するわけです。この幸子のトリックは、人ごとが我がごととなるこの映画のテーマそのものではないか。あのトリックにこの映画の物語全体が要約されている。そう考えてみると、あのトリックのシーンが非常にスリリングに見えてきました。
今までは『彼岸花』のストーリーに注目しながら、そのストーリーがどれだけ緻密に組み立てられているかを見ていったわけですが、もちろんそれは『彼岸花』のまったくの一面にしか過ぎないわけです。しかも、ストーリーから見るといっても、これもある一つの立場から見たに過ぎない。皆さんにはもう一度『彼岸花』という映画を思い返していただいて、皆さんなりの小津映画の厳しさ、緻密さを考えていただけたらなあと思っています。今までの話とは少しずれるんですけれども、もう一つだけ気づいたことがあります。「導入」のところでこの映画の主要人物たちが紹介されていく。次から次へとおかしなエピソードによって人物たちが紹介されていくわけですけれども、その紹介の仕方にある法則があります。まず結婚式のシーンですね。中村伸郎が演じる河合の娘の結婚式です。笠智衆が演じることになる三上のことが噂されます。三上は来ていないね。三上はどうしたのかね。そこにはいない人のことがまず話されるわけですね。次の「若松」のシーンでも三上のことが話題にのぼります。また、平山の娘、節子の話もでます。そこにはいない人物が噂されるわけですね。その後で、平山が家に帰ってきて、有馬稲子が演じる節子本人が映画に登場します。まず噂話で紹介され、その後で本人が登場する。三上も同じ道筋を辿ります。河合の娘の結婚式、「若松」のシーンで噂話として紹介された後で、平山の会社を訪ねる本人が登場する。最初に本人がドンと現れて、あれは誰、私はこういう者です、というわけではない。浪花千栄子は突然現れるんですが、その娘である幸子もやはりまず噂話で紹介される。噂話が先で、その後で本人が登場するということになるんですね。問題は谷口です。この映画の流れを大きく変える人物の一人が谷口なんですけれども、この谷口がどのように映画に登場するかと言うと、彼は他の主要登場人物の道筋を辿らない。いきなり登場する。彼は誰だ? 観ている方も分からない。それは平山の驚きでもあるでしょう。突然、今まで知らなかった男が現れた。それまでの、馴染みの人たち同士の和気あいあいの感じ、人ごとが無責任に笑い飛ばされるような世界がガラッと変わる。巧妙に練られた登場の仕方だと私は思いました。谷口が平山に名刺を渡して、私は谷口という者ですと自己紹介する。その平山と谷口の一対一の対決シーンが、そのように準備されていたわけです。後で気づいたのですが、この映画において、平山と谷口が会うのはこのシーンだけですね。平山は、娘の問題をめぐってもっとも対立する人物、谷口とはここ一回きりしか会っていない。それにしては平山にとっての谷口の印象はもの凄く強いわけですけれども、それはやはり谷口との出会いのインパクトが後にひいているのかなあと思いました。
今日お話できることはだいたいこの辺りでございます。映画美学校の授業という機会があって、一本の映画のストーリーを細かく見ていく作業をしてみたのですが、やってみると思いもつかなかったようなことが分かってきました。また、いろいろと考えた後でもう一度映画を観ると、今まで見えていなかったことが見えてもきました。皆さんも試してみると面白いのではないかなあと思います。以上です。今日はどうもありがとうございました。