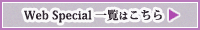講演
「つなぐことはまぜること 『リオ40度』を巡って
――ネルソン・ペレイラ・ドス・サントス 講演と上映シリーズ」
2002年5月17日
とちぎあきら(映画研究者)
私はこの数年、「アモス・ギタイ映画祭」や「イスラエル映画祭」、それからその近隣のアラブ諸国の映画の特集、「地中海映画祭」といった企画に携わってきました。ブラジル映画については門外漢です。ただし、2000年にネルソン・ペレイラ・ドス・サントス監督のレトロスペクティヴが開催された際、プレス資料を作るために映画を見たり、調べものをしたりしたんです。そのときに発見したことを話しませんか、ということで今日ここに呼ばれたんだと思っています。これから上映いたします『リオ40度』の詳しい分析や批評は私の手に余りますので、このネルソン・ペレイラ・ドス・サントス監督という人はどういう経歴の持ち主か、そして監督の作品のこんなところに注目すると面白いんじゃないか、というお話をさせていただこうと思います。
はじめに、地中海のことから話をさせてください。2000年の春に国際交流基金が「地中海映画祭」を開催したんですけれども、その前年の1999年に地中海の五カ国をまわって作品を選定したんです。非常に駆け足の旅行だったんですが、トルコ、ギリシャ、それからモロッコ、チュニジア、シリアというアラブの国々をまわって新作映画を見ました。トルコでは、首都のアンカラにアタチュルク文化センターというトルコ映画を海外に紹介するための組織がありまして、そこで編集機を使って映画を見せてもらいました。モロッコでは、首都ラバトにシネマテーク・マロケインというアーカイブがありまして、そこでビデオを見せてもらって、また、それとは別に第七芸術劇場という映画館でも映画をフィルムで見ることができました。それから、シリアの場合は国立映画総局というのがあって、非常に小さな応接室のような試写室で映画を見たり、編集室で映画を見たりしました。シリアでは国が90%の映画を作っていて、映画監督、スタッフ、キャストのほとんどが公務員なんです。それはともかく、各国で映画を見せてもらっているうちに気がついたのですが、トルコ、モロッコ、シリアで使われている映写機や編集機が、どれもイタリア製なんです。映画の編集についてご存知の方は、編集機というテーブル状の機械の上にフィルムのリールを横に寝かせて、テーブルの上のモニターを見ながらフィルムを操作して、カットしたり、接合したりする箇所を選ぶ、という作業がイメージできると思います。その編集機が、どれも「プレヴォスト(Prévost)」というメーカーの製品で、イタリア製なんですね。僕はこういうことにあまり詳しくないのですが、日本で一番普及しているフィルム編集機はドイツ製の「ステンベック(Steenbeck)」だと思います。ところが、それらの国々ではそのプレヴォストでして、さすが地中海、イタリアなんだなあと思いました。イタリア映画は、サイレント映画の時代からネオレアリズモ、その後の巨匠たちの時代、と常に存在感があって、それらの映画が近隣諸国に影響を与えていることは推測できるのですが、映写機や編集機といった機材にまで、イタリアの覇権とでも言いましょうか、影響が及んでいることに、そのとき感じ入りました。その後、そのことは忘れていたのですが、ネルソン・ペレイラ・ドス・サントス監督のレトロスペクティヴのために色々と資料を読んでいたとき、不意にこんな文章に出くわしたんです。あるアメリカの映画研究者が監督にインタビューをしていて、『狂ったアジーロ』という69年の作品とその頃のことを話している。これは監督のはじめてのカラー映画なんですが、それはともかく、この69年頃に編集に関して大きな変化があった、と言っています。映画の編集とはフィルムを切ったり、貼ったりするわけですが、昔はアセトンでできたフィルムセメントで接着していたのが、その頃からスプライシングテープというフィルム編集専用の透明なテープができて、それを使うようになった。それから編集機についても、それまではフィルムのリールを縦に並べて動かしていたのに、その頃から横に寝かせて作業するようになった。縦を横にしたのはイタリア人だと思う、とも言っていました。お、ここでまたイタリアか、と思ったわけです。来日した監督の姿を見たら、町の工務店の社長のような、ジャンパーのポケットから今にも色んな工具を取り出しそうな職人タイプの人物で、そのインタビューで編集について、技術について熱く、楽しそうに語っていたことが、なるほどと納得できました。
監督がそのインタビューで編集のことを熱く語っているのは、これからご覧いただく『リオ40度』という長篇デビュー作を発表する前の経歴と関係があるように思うんですね。ここで監督の経歴を振り返ってみたいと思います。ネルソン・ペレイラ・ドス・サントス監督の父親はフリーメイソンの家族によって育てられた孤児で、母方はイタリア系移民の出身です。こういう家庭環境から考えると、宗教的な戒律の厳しい家庭を想像しますが、実際はそれとは反対に、両親は非常にプラグマティックな考えの持ち主で、子どもの頃は週に二回ほど家族で映画館に通ったりもしていたそうです。その後、ブラジルのエリート養成校であるサンパウロ法科大学に通って、法律関係のことを学ぶ。それが第二次世界大戦の直後です。第二次世界大戦が終わるまでの約15年間、ブラジルではジェトゥリオ・ヴァルガスという独裁者による政権が続いていて、『監獄の記憶』で描かれているような共産主義者への弾圧、思想や言論の自由への抑圧が起こっていた。その後の民主化要求などが叫ばれる時代に、大学に入学。共産党の青年運動にも参加したようです。47年に共産党がブラジルで非合法化され、その影響もあったのか、49年にフランスに留学します。フランスではたくさん映画を見ます。シネマテークにも通ったようです。それから、サルトルに代表される実存主義の思潮などにも触れています。つまり、青春期にブラジル、そしてパリで戦後の激動を経験したわけですね。50年にブラジルに帰国して、弁護士やジャーナリストとして活動しながら、自主製作の16ミリ映画を撮ります。それは『青春』というタイトルの中編ドキュメンタリーで、監督はそのときのことを「自宅の寝室で、手探りで編集作業をしつつ、まるで火薬の取扱いを学んでいるような気がした」とあるインタビューで述べています。もちろん、この発言には政治的なニュアンスが含まれていると思いますが、フィルムというモノの歴史をご存知の方には、監督が映画を作りはじめた時代のフィルムは、まだナイトレート・フィルムと呼ばれる可燃性フィルムだったことにも思い当たるでしょう。もちろん、16ミリフィルムは当時から不燃性フィルムだったはずですが、火薬という喩えはそう突飛ではないと思います。また、この言葉は監督が作ろうとした『青春』という映画の内容にも関わっています。この『青春』という映画は、サンパウロに暮らす若者が同じ年代の友人に手紙を書くという設定で、ブラジルのさまざまな若者像を描いています。ネルソン青年も学業を終えたばかりで、自分とほぼ同世代の若者を描こうという思いがあったのでしょう。1950年は朝鮮戦争が勃発した年で、当時の親米的な政権下でブラジルは動員に協力しており、そのため兵役の期間が延長されて、ブラジルの若者の間ではそのことが大きな問題となっていた。この映画を作っていた頃、本人も軍属の身分にあって、内地の兵舎で生活していたようなんですが、そこではいろいろな演習が行われる。大砲による砲撃の演習も行われ、それを撮影した。その砲撃のショットと、サンパウロの工場の煙突がもうもうと煙を吐き、炎をあげているショット――それを繋ぎ合わせて、街全体が砲撃を受けて燃え上がっているシーンを作れないか、と考えたらしいんですね。そのイメージが閃いたことで、編集とは何かということをはじめて発見した、と監督は言っています。編集によって、調合された火薬のように、イメージの起爆力、爆発力、炸裂する力が生まれるということを発見した、と言っているんですね。その後、ペレイラ・ドス・サントスはリオ・デ・ジャネイロに移り、何本かの商業映画の助監督を務めます。そして、リオの山間にへばりつくように生活している人々の集落、そのスラムは「ファヴェーラ」と呼ばれているのですが、そこを知って、そこの人々と生活を映画にしたいと思うようになります。それが『リオ40度』として結実するわけです。このように、監督としてデビューするまでの過程において、編集というものがとても大きな意味を持っている。60年代に「シネマ・ノーヴォ」という若い映画作家たちによるブラジル映画の新しい運動がはじまりますが、そこでもペレイラ・ドス・サントスはグラウベル・ローシャ監督の処女長篇とか、レオン・イルツマン監督の短篇作品の編集を引き受けている。彼が映画の世界に入っていく、映画の世界で生きていく上で、編集はひとつの大きな鍵だったんですね。
ただし、先ほど申し上げました、平台型の編集機を発明したのはイタリア人なのかという問題は、まだ答えが見つかりません。いろいろと調べたんですが、どうもはっきりしない。私は東京国立近代美術館フィルムセンターという所に勤務していまして、そこにステンベックがあり、出入りの業者さんもいますので、その人にも聞いてみたんですが、確かにプレヴォストというメーカーは存在していて、日本に輸入されたこともあるとは言っていましたが、それぐらいしか分かりませんでした。映画美学校で講師もされている筒井武文さん、映画作家であり映画編集者でもある筒井さんに聞いてみたら、同時録音の場合、画のフィルムと音の素材を同時に動かして編集しなくてはならず、そのためには卓状の編集台の方が便利ということでデザインが変化したんだろう、というお返事でした。ただし、イタリアはずっとアフレコが主流だから、イタリア人が発明したというのは本当かなあ、と首を捻っていましたね。映画の編集や機材の発達史に詳しくて、この真偽をご存知の方がおられましたら、ぜひお知らせください。
ところで、ペレイラ・ドス・サントスと編集という点から、作品を仔細に論ずるというのは私の手に余りますが、『リオ40度』という映画の構成については、多少関連付けてみることができると思います。『リオ40度』を作るにあたって、ある文学的記憶がヒントになった、とペレイラ・ドス・サントスは言っています。ジェイムズ・ジョイスの「ユリシーズ」のような映画を作りたいと思ったそうです。つまり、たくさんの登場人物がいて、特に子どもたちが登場して、彼らの姿を点描しながら、リオのある一日をいろいろな人たちがどのように過ごしたのかを描きたい、と思っていたらしいですね。リオ・デ・ジャネイロという都市に生きる人々の姿をモザイクのように描き出すこと。ファヴェーラに生きる少年たちの姿によって都市を描くこと。そういったことを、ジョイスを援用して表現しようと思ったわけです。また、この『リオ40度』には、文学だけでなくて映画的なバックボーンもあったと思います。ペレイラ・ドス・サントスはパリ留学中にシネマテーク・フランセーズなどでたくさんの映画を見ました。とりわけ、イタリアのネオレアリズモ、ヴィスコンティやロッセリーニの映画をほぼ同時代に見て、大いに触発されたそうです。きっとそれだけではなかったでしょう。『リオ40度』は都会で生活する人々をモザイクのように描き出すわけですが、かつてヴァルター・ルットマン監督が『伯林―大都会交響楽』という映画を作った頃から、都会のさまざまなものを点描する映画として「シティ・シンフォニー」「都市交響楽もの」というスタイルが発展し、1934年には、ロバート・シオドマーク、エドガー・G・ウルマーたちが『日曜の人々』という映画を作ります。やはり、都会の人々の一日を描いた作品です。このような、いわゆる都市映画の記憶も『リオ40度』の出発点にはあったのではないか。そして、最後にもうひとつ言えることは、ペレイラ・ドス・サントスが『リオ40度』を製作する前に、三本の映画の助監督を務めていたことです。その三本はミュージカル、それも「チャンチャーダ」と呼ばれるブラジル映画独特の、カーニバルを取り込んだミュージカル映画でした。カーニバルの音楽、踊り、衣装、風俗を中心に据え、コメディタッチの物語が展開する娯楽映画の一ジャンルで、1930年代頃に生まれたといいます。このジャンルの映画は季節ものでして、11月頃に企画され、12月に撮影を行って、2月に行われるカーニバルの少し前に上映される。そこでは人気のミュージシャンや踊り子、作曲家による新曲も披露され、カーニバルの前夜祭のような感じで、人物、音楽、流行を紹介するPR映画でもある。ペレイラ・ドス・サントスは、こういったチャンチャーダ映画にスタッフとして参加し、ジャンル映画の規範を身につけた上で、デビュー作『リオ40度』に取りかかったのではないか。つまり、さまざまな要素を混在させつつ、それらを編集で繋いで、ファヴェーラというスラムに住む低所得者層、多くは黒人の居住者たちの共同体的なアイデンティティを映画のなかで発揚させていく、こういう映画の作り方を身につけていったんじゃないかと思えるんですね。
ファヴェーラに住む人々に向けて焦点が絞り込んでいく作品の構造、それは『リオ40度』が作られた状況、時代的な文脈と深く関わっている、と監督が先ほど引用したインタビューで話しているので、この映画の背景についても少し紹介してみましょう。ペレイラ・ドス・サントスは、カーニバル映画の助監督を務めていた頃に『リオ40度』の着想を得ました。53年に脚本を書き、54年に撮影をはじめて、55年に映画を完成させた。これだけ時間がかかったのは予算が無かったからですね。製作費が少なかったので、どうしたかというと、この映画に関わるスタッフ、キャストにまずは労働を無償で提供してもらい、債券を買ってもらって、それにしたがって公開時に発生した利益を分配し労働の報酬とするという、生活協同組合のような方式を採用したわけです。それで映画が完成したとき、どこの誰かは分からないと監督は言っていますが、あるところから共産主義的映画だと非難された。当時のブラジル映画には検閲があって、撮影前の脚本段階で撮影許可、上映許可を得てから撮影に入るのですが、『リオ40度』も当然、許可を得た上で作られていながら、共産主義的という非難もあって、公開禁止になった。ブラジルのネガティヴな面が多く描かれている、世間の人々の騒乱を煽るものであるとして、連邦警察の長官が公開禁止の処分を下したんです。この映画はアメリカのコロンビア映画が権利を取得していて、そのブラジル支局が国内や世界での配給権を持っていたようですが、この公開禁止によって、コロンビア映画ブラジル支局長がアメリカの FBI から尋問を受けるという事態にまで発展しました。このような由々しき事態となったのは、当時のブラジルの時代的な状況にあったと言えます。先に言いましたように、ブラジルは第二次世界大戦が終わるまで、1930年から15年間、ヴァルガスという人物の独裁下にあった。一時、政権を降りたものの、1950年に返り咲くんですね。ところが、軍部と折り合いが悪く、軍部から圧力を受けたことで、『リオ40度』を撮影している54年に、ヴァルガスは自殺をしてしまう。それに乗じて政権を奪取しようとする動きも軍部にはあったようですが、大衆の反発を受けてクーデターには至らず、結局選挙になります。すると、軍に対する反発が幅広い層に生じて、かなり右翼的な勢力から共産党に至るまでの反軍部の統一戦線が組織されるんですね。その陣営は、後に大統領となるジュセリーノ・クビチェックを擁立して選挙に臨みます。この選挙戦が加熱していた55年に『リオ40度』は公開禁止となり、そのことが大々的に報道されました。待ってましたとばかり、統一戦線側が抗議し、『リオ40度』の公開を求め、それが選挙の争点のひとつになっていくんです。一本だけあったプリントを反軍部側の政治家、知識人、メディアに見せて、選挙戦の争点としてこの映画を公開しようという運動が作り出されたわけです。クビチェックを大統領にしたいという勢力はブラジル国内に広がっており、この一本だけのプリントを各州に送って、シネクラブやホールで上映して、この映画の一般公開を求める運動が広がっていった。その頃、各州のシネクラブには、たとえばバイーア州にはグラウベル・ローシャ、リオ・デ・ジャネイロにはレオン・イルツマンやジョアキン・ペドロ・デ・アンドラーデ、カルロス・ディエギスなど後に監督となる若者たちがいて、その上映会に監督自身が足を運び、彼らと知り合ったことが、シネマ・ノーヴォの発火点となったという事実があります。『リオ40度』は、ブラジル映画史において非常に重要な作品です。さまざまなジャンルを混ぜ合わせたような構成やカーニバルの歌や踊りの見せ方といった映画それ自体の魅力とともに、政治と映画との抜き差しならぬ関係、後に起こるシネマ・ノーヴォ、ブラジル映画史との関係、そういったさまざまなコンテキストを、この映画に看て取ることができるわけです。
ここで、ちょっと唐突ですが、『リオ40度』の多面体的な特徴をより良く理解できるかもしれない一つの補助線を紹介します。それはオーソン・ウェルズです。ウェルズは映画史における巨大な存在ですから、その全貌を捉えたうえでお話するわけにはいきませんが、ブラジルとの関係で言いますと、ウェルズは『偉大なるアンバーソン家の人々』の撮影直後にブラジルに渡ります。ブラジルとその他の中南米の国々を舞台にした幾つかのエピソードからなる『イッツ・オール・トゥルー』を作るためで、結果的にそれは未完に終わりますが、その製作状況には『リオ40度』と共振する、似通った部分が多く見られます。
『イッツ・オール・トゥルー』は42年に撮影に入りますが、その一年ぐらい前からハリウッドの撮影所内にあった企画だと言われています。41年と言いますと太平洋戦争勃発の年ですが、その年の末、ウェルズは、ネルソン・ロックフェラーという財界の大ボスがリーダーを務めるアメリカ政府内の政治部局 Coordinator of the Inter-American Affairs(CIAA、アメリカ大陸間問題調整局)の善隣大使に任命され、アメリカ合衆国と中南米を舞台に四つのエピソードからなる映画として構想されていた『イッツ・オール・トゥルー』の製作に乗り出します。この CIAA ができた背景を説明しますと、ルーズベルトが1933年頃から Good Neighbor Policy(善隣外交)という政策を打ち出します。近隣のラテンアメリカ諸国ともっと協力関係を築こうという施策ですが、これはある意味で建前でして、大恐慌を迎えたルーズベルト政権が中南米の市場をより開拓したいと考え、このような外交方針を立てたわけです。ところが、1939年にヨーロッパで第二次世界大戦が勃発し、枢軸国のドイツとイタリアは中南米に接触して、とりわけブラジルのヴァルガスはかなり親ドイツ的になっていました。ルーズベルトは危機感を募らせ、それで40年に CIAA を立ち上げるわけです。
この CIAA がやったことのひとつに情報政策があります。それは、出版、放送、映画などのメディアを通じて中南米の国々に、中南米諸国の利益とアメリカの利益は一致するとアピールし、ヨーロッパの国々の影響を排するために、アメリカびいきのニューズリールや観光映画をたくさん作って上映し、アメリカに対する印象を良くしようとした。ちょうどその頃、ハリウッド映画はヨーロッパでの戦争により市場が逼迫し、これまで以上に中南米に映画を輸出したいという思いがあった。加えて、ロックフェラーは映画会社 RKO の筆頭株主で、その RKO と契約していたマーキュリー・プロダクションはオーソン・ウェルズが主宰していた映画会社ですから、したがって CIAA が企画する映画の切り札にはウェルズが適任、ということだったようです。もちろん、ハリウッドはそれ以前から善隣外交の流れに乗って、ドロレス・デル・リオというメキシコ人の女優を起用したり、ブラジルのミュージシャンで女優のカルメン・ミランダを主役に迎えたラテンものの映画を結構作ったりしていましたが、さらに本腰を入れて、この傾向の作品を作っていこうと考えたわけです。ところが、ブラジルに渡ったウェルズは、ハリウッドの重役や CIAA の役人の思惑とはまったく違ったことをやりはじめた。ドロレス・デル・リオやカルメン・ミランダが主演したラテンものの映画は、ハリウッドのスタジオのなかで架空の想像上のラテンアメリカの国を作って、歌い、踊り、ラテンアメリカの国々のさまざまな文化の実相を、かなり無視した映画だったわけですが、ウェルズはすべて現地ロケーションで映画を作ろうとした。さらに、現地で募った専門家にさまざまな調査を依頼し、その結果を企画段階から取り入れようとしたんです。たとえば、サトウキビやコーヒーの生産とか、奴隷制度の歴史とか、鉱山やその他の資源、産業の実態とか、リオのカーニバルとか、ブラジルのさまざまな側面を専門家に調査させて、それらを映画作りの土台にしようと試みたわけです。ハリウッドの脚本家の手による手馴れた脚本を基にした映画、とは違うものを作ろうとしたんですね。そして、映画に多くのミュージシャンや素人を登場させようと考えたようです。ハリウッドのメソッドとはまったく違う、ニュース映画を拡大したような、ひとつひとつのトピックからなる雑誌の特集記事のような映画を作ろう、とウェルズは構想したらしい。ウェルズではなく、ノーマン・フォスターという監督がメキシコで撮った『我が友ボニート』という短編を映画のなかに組み込もう。ウェルズがブラジルに渡る直前に、四人の漁民が待遇改善を求めて筏に乗り、海岸線沿いに2600キロを航海したのですが、これを映画で再現しよう。そして、リオのカーニバルを題材にしたパートも撮影しよう、と考えたようです。それで、実際にファヴェーラに住んで、いろいろな調査をしたり、人々と知り合って寝食を共にしたりするなかで、リオのカーニバルがブラジル文化の本質を体現したものであることを、ウェルズは発見するんですね。これからご覧いただく『リオ40度』でも描かれていますが、リオのカーニバルとは、それぞれの町、地域にある escuela de samba と呼ばれる、「サンバ学校」とよく訳されるのですが、実際は町内会のようなサンバのチームで、今年はこういう曲で、こういう振り付けで、こういう衣装でといったことを決め、パレードでどのチームが一番良いかを競い合う、そういう競技会なんですね。その競技会で披露される踊りとか歌というのは、ブラジルは18世紀の終わりに奴隷解放を行うのですが、その頃からリオのファヴェーラに住みはじめた、主に黒人の居住者がはじめた歌や踊り、衣装が起源で、女装男装などの異性装が普通に行われる空間、それがカーニバルだったんです。セクシュアルな境界と、人種的、民族的な境界線を取り払って、ある架空の、そして一瞬のユートピア世界を作りあげるのがカーニバルの本質ではないか――ウェルズはそう考えたんですね。彼はさらにもう一歩踏み込みます。カリブ海のハイチには、白人によって原住民のインディオが虐殺され、その後、黒人が奴隷として連れてこられた歴史、そのインディオの受難、悲劇の記憶を黒人たちが継承していったブードゥーという呪術がありますが、そのブードゥーこそがカーニバルのルーツじゃないか、とカーニバル論を発展させていく。ここでウェルズに詳しい人はピンとくるかもしれませんが、彼は『市民ケーン』の前の1936年に、ハーレムのラフィエット・シアターでシェイクスピアの「マクベス」をすべて黒人のキャストで演出しています。これが彼の本格的な演劇活動のはじまりです。この芝居は「ブードゥー・マクベス」と呼ばれていて、つまり、ブードゥーとシェイクスピアの「マクベス」をミックスすることから、ウェルズの本格的な演劇活動は始まっているんですね。そんな彼がカーニバルの地に来て、いろいろな発見をするわけですが、そのフッテージが RKOのプロデューサーにはよく理解できなかったようです。単に黒人たちがはしゃいで歌って踊っているだけにすぎないと思われてしまった。カーニバルのシーンだけテクニカラーのシネマスコープで撮ったと言われているんですが、結局RKOが倒産して、そのフィルムは海に捨てられたと言われています。1980年に『イッツ・オール・トゥルー』の断片が発見され、筏に乗った漁民のエピソードの部分が比較的たくさん残存していたので、それを復元して『イッツ・オール・トゥルー』についてのドキュメンタリーが製作されました。日本でも95年に劇場公開されています。
ウェルズの話を延々としてしまいましたが、ウェルズとネルソン・ペレイラ・ドス・サントスとの間に直接の関わりがあったかというと、僕は大した調査もしておりませんので分かりません。ペレイラ・ドス・サントスがウェルズの作品から何かを得たという証言も知りません。ただし、ふたりを結びつけたと考えてもおかしくはない、非常に重要な人物が何人かいます。
ひとり目は、ペレイラ・ドス・サントスがチャンチャーダ映画のスタッフだったときに、その映画の監督だったアレキス・ヴィアニという人物です。彼はもともと映画ジャーナリストで、ブラジル映画史についてのテキストも残した批評家でもあり、かつ映画作家です。先ほど、ウェルズがブラジルでいろいろな専門家たちの意見を聞いたと言いましたが、その専門家のひとりがヴィアニでした。彼はチャンチャーダ映画の監督ですから、カーニバルに詳しく、綿密な報告書をウェルズに提出したようです。リオのカーニバルは、ファヴェーラに住む黒人たちが作り出した踊りやスラング、語り、衣装を起源とし、その発祥の地である山肌のファヴェーラから、麓に住んでいる白人や混血の人々、ムラートと呼びますが、そういった人々へとどんどん浸透していって、いわゆるカーニバル的な空間を形成した。そういう表現なのだということを、ヴィアニはレポートしたと言われています。ヴィアニはウェルズのことを、外国人では誰よりもカーニバルに熟知した人物だった、と回想しています。
ふたり目は、グランデ・オテロというブラジル映画には欠かせない俳優です。彼は、30年代からナイトクラブで芝居をしたり、舞台で演劇を行ったりしていた、チャンチャーダ映画には欠かせない喜劇役者です。このグランデ・オテロを、ペレイラ・ドス・サントスは『リオ40度』の次の映画『リオ北部』で、主役に起用しています。残念ながら、僕は『リオ北部』を見ていないので、書物からの知識なんですが、これは『リオ40度』以上にイタリアン・ネオレアリズモの影響が強いと言われています。にもかかわらず、ミュージカル映画の常連俳優であるコメディアンを主役に据えている。ペレイラ・ドス・サントスは、80年代にもこのグランデ・オテロを起用しています。オーソン・ウェルズは『イッツ・オール・トゥルー』のカーニバルのシーンを、彼をメインにして撮影したそうです。ウェルズはグランデ・オテロのことを、世界でもっとも優れた喜劇俳優でマルチタレントな役者、若き日のチャップリンにも匹敵する、と絶賛しています。また、偶然ではありますが、このオテロ、英語で言えば「オセロ」ですから、シェイクスピアにちなんだ名前ですね。オセロがヴェネツィアのムーア人であるように、彼もブラジルの黒人です。
最後は、ヴィニシウス・ヂ・モライスという人物です。映画史においては、前に紹介したふたりよりもよく知られています。彼は、ウェルズが『イッツ・オール・トゥルー』を撮っていたときに、映画評論家としてその動向を逐一報道し、ウェルズ本人とも懇意に付き合い、文章をたくさん残しています。後に音楽の世界で、アントニオ・カルロス・ジョビンというボサノヴァの有名なミュージシャンと仕事をしたりします。詩人でもあり、劇作家でもあります。59年にフランス人のマルセル・カミュ監督が『黒いオルフェ』という映画を作りますが、その原作者がヴィニシウス・ヂ・モライスです。ギリシャ神話の世界とその登場人物を、ブラジルのファヴェーラとそこに住む黒人ミュージシャンに置き換えて、ある悲恋を描くわけですね。このヴィニシウス・ヂ・モライスが、かつてウェルズに対して非常に大きな共感と理解をもって『イッツ・オール・トゥルー』の製作をルポしていたことから、ウェルズがシェイクスピアにブードゥーを混交させてオール黒人キャストで演出したように、彼はリオのカーニバルにギリシャ神話を導入して、この『黒いオルフェ』を構想したのではないか。ヴィニシウス・ヂ・モライスの発想の原点はウェルズにあったのではないか、と思えるんです。この『黒いオルフェ』は、99年に『オルフェ』というタイトルで再映画化されました。この新しい『オルフェ』を監督したのは、カルロス・ディエギスという、先ほど紹介した『リオ40度』の影響を受けて登場したシネマ・ノーヴォ世代の映画作家です。このヴィニシウス・ヂ・モライスを介して、ウェルズ、ペレイラ・ドス・サントス、そしてシネマ・ノーヴォの映画人へと繋がっていくのではないか、とも思えます。
カーニバルがブラジルの黒人の文化、記憶、アイデンティティの発現の場であったという発見。そして、黒人たちが継承してきた文化を白人やムラートたちが吸収して、また新たなカーニバルを生み出していくダイナミズム。それを、ペレイラ・ドス・サントスもブラジル文化の本質として考えたのではないでしょうか。その、本質としての混血性とでも言うべきものを探究していくことが、その後の彼の映画作りの大きな柱になっていったのではないか。これから上映いたします『リオ40度』には、チャンチャーダ映画のミュージカル性やネオレアリズモの影響が顕著ですが、63年の『乾いた人生』を経て、70年代の『オグンのお守り』や『奇蹟の家』といった映画で、ネルソン・ペレイラ・ドス・サントスは、ブラジルの宗教や文化の深層に分け入っていきます。そのときのキーワードは、やはり「混血」ではなかったかと思いますし、そのはじまりは『リオ40度』であり、仮説ではありますが、オーソン・ウェルズを通じて手渡されたカーニバルの発見にあったのではないでしょうか。「まるで火薬の取り扱いを学んでいるよう」だと感じた編集作業により発見した映画の爆発的な力を、ネルソン・ペレイラ・ドス・サントスは『リオ40度』において、多くの人たちが交錯する物語のなかに、とりわけその物語の焦点となっていくカーニバルの描写のなかに、体現したのです。