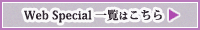講演
「ロシア革命と映画――ロシア・ソビエト映画祭 第二回東京上映会」
1999年6月26日
山田和夫(映画評論家)
山田和夫です。この「ロシア・ソビエト映画祭」は、数は少ないですけれども日本で初めて上映される帝政ロシア時代の映画、それから革命後の作品であっても日本で一度も上映されたことがなかった映画で編成されておりますので、それらを理解していただくのに参考になるようなお話をしてみたいと思います。終わりの方では、この後で参考上映いたします『虹の世界のサトコ』とその監督のアレクサンドル・プトゥシコについてお話いたします。
1995年が映画の生誕100年でして、映画が誕生した次の年にはロシア映画の歴史もはじまっています。映画の100年を記念して、ロシア映画の100年も日本に紹介してみたいということで、本当に不十分な数なんですけれども15本ばかりの映画を選んだのがこの「ロシア・ソビエト映画祭」です。モスクワの郊外にゴスフィルモフォンドという、元はソ連邦国立ですけれども、ロシア国立のフィルムライブラリーがあります。規模は世界最大です。何しろフィルムライブラリーとそこで働いている人のために一つの町ができているんですね。従業員だけで650人。世界のフィルムライブラリーのなかではフランスのシネマテーク・フランセーズが大変有名でして、質的にも非常に高いのですけれども、そこでも働いている人は100人ちょっと。日本では東京国立近代美術館フィルムセンターが唯一の国立の映画保存所ですけれども、職員はわずか11人。もう比較しようがない状況なんですね。その世界最大のフィルムライブラリー、ゴスフィルモフォンドへ行くと観たい映画が何でも観られる。内外の映画55,000タイトルあるわけですからね。フィルムが残存している帝政ロシア時代の映画はもちろんそこに全部ある。革命後の映画も若干欠けてはいますが、ほぼ全部ある。そこで数十本の映画を観たなかから、この「ロシア・ソビエト映画祭」のために15本を選んだというわけです。
革命によってソビエト映画が生まれて、それが世界的にあまりにも有名になった。どの国の映画史のテキストを紐解きましても、1920年代から30年代のはじめはソビエト映画の黄金時代であったとして、ソビエト映画のもの凄い高揚、世界の映画に与えた貢献がかなりのページを使って書かれている。それがあまりにも有名になったために、それ以前の革命以前の映画のことはあまり注目されてこなかったんですね。アメリカに有名な映画史家であるジェイ・レイダという人がいます。ジェイ・レイダは、30年代はじめにソビエトの国立映画学校に入学して、エイゼンシュテインの教室で学んだ非常に珍しい経歴の研究家です。エイゼンシュテインの論文などをアメリカやイギリスの英語圏に紹介し、エイゼンシュテインのことを広めた最大の功績者ですけれども、この人は当然ながらロシア・ソビエト映画全体を非常によく研究しておりまして、60年代の終わりに「キノ―ロシア・ソビエト映画史」という、残念ながら日本で翻訳されておりませんけれども、言わばロシア・ソビエト映画史の定本と言っていい本を書きました。その後、二回ぐらい改訂増補版が出版されていますが、私は全部持っております。私はモスクワ映画祭ではじめてジェイ・レイダさんにお会いして、ニューヨークに行ったときにはご自宅へお邪魔したりもしました。その彼が「ロシア・ソビエト映画史」で書いた大切なことの一つは、革命前のロシア映画と革命後のソビエト映画の間には確かに飛躍があるけれども、断絶だけを強調するのは間違いだということですね。つまり、革命前の時点でロシア映画はかなりの程度まで発展していて、何人かのベテランの映画人たちは革命後もソビエト映画の建設に大変な尽力をした。だから、飛躍だけを強調するのは正しくないということです。「ロシア・ソビエト映画史」はこんな分厚い本ですけれども、その四分の一ぐらいは革命前の映画のことに費やしている。それは画期的なことなんですね。
その革命前の映画のうち、たった四本しかこの「ロシア・ソビエト映画祭」では上映できないんですけれども、最初の劇映画と言っても10分ぐらいの『ステンカ・ラージン』、最初の長編と言っても一時間もない『セヴァストポリの防衛』がその四本のうちの二本です。それから、ロシア・サロン映画と言われたんですけれども、ロシアの上流階級、貴族階級を舞台にしたメロドラマ、あるいはロシアの文芸作品を映画化した作品がこの時代にたくさん作られていて、なかにはちょっと面白そうな作品もあって、例えばトルストイの「戦争と平和」を映画化した作品でたった10分というのがあるんですね。信じられないわけでして、ご存知の通り、トルストイの「戦争と平和」を映画化した7時間5分というソビエト映画の超大作があります。それですらダイジェストにならざるをえないのに、10分間で何をどう見せているんだろうか。そのような作品がごろごろあるんですね。今回の映画祭のためにその種の作品を持ってくることは叶わなかったんですが、ロシア・サロン映画の水準を示す作品として、『人生には人生を』というエウゲニー・バウエル監督の代表作の一本をプログラムに入れました。それからもう一作品はアニメーションですね。ヴワディスワフ・スタレーヴィチという名前からしてお分かりのようにポーランド系のロシア人ですけれども、このスタレーヴィチは世界的な人形アニメーションの改革者なんですね。この人の作った『カメラマンの復讐』では、トンボだとかカブトムシだとか、そういった虫の人形、模型を動かして不倫物語が描かれます。今観ても吹き出すような面白いお話なんですけれども、虫の動きが実に精密なんです。残念ながら、スタレーヴィチは革命後にパリに亡命して、フランスで仕事をしています。そのスタレーヴィチの代表作である『カメラマンの復讐』を今回のプログラムに入れました。
『人生には人生を』や『カメラマンの復讐』を観ましたら、帝政ロシア時代の映画がかなりの程度発達していたことがお分かりになると思います。ただ、ご存知の通り、当時1億5000万ぐらいの人口があったんですが、都会の住民はほんのわずかなんです。革命のときもそれが一番の問題になったわけですけれども、大都会で働いている労働者階級は300万人しかいなかった。圧倒的に多いのは農民であって、字も読めないし、もの凄く貧しくて遅れた生活を強いられていた。帝政ロシアの映画が発達していたとしても、非常に限られた層にしか受け入れられていなくて、農村で映画を観るなんてことは本当に考えられない状態であったわけです。当時の大都会であるモスクワだとかサンクトペテルブルグだとかには結構な数の映画館があって、ヨーロッパやアメリカの映画も上映していて、そして国産映画も上映されていたわけですけれども、大都会の人は年に何回も映画を観ているけれども、生涯まるっきり映画に触れないで死んでいった農民は非常に多かったのではないかと思います。その時代と革命によって開かれたソビエト映画史との間には、確かにやはり断絶と言っていいような大きな飛躍があります。ただ、帝政ロシア時代から美術監督として活躍していたレフ・クレショフは、革命後、ソビエト映画の最初の建設者の一人になるわけですし、「スペードの女王」というプーシキンの原作を映画化したヤーコフ・プロタザーノフは、一時パリに亡命したんですがすぐ帰国して、ソビエト映画の建設者の一人になるわけですね。帝政時代のかなり優れた映画人の何人かが、ソビエト映画の建設に貢献したという事実があります。
1917年11月にロシア革命が成功し、ソビエト政権ができるんだけれども、もう1918年のはじめから東西南北の14ケ国の資本主義の国々がロシアに攻め込みます。生まれたばかりの社会主義共和国を双葉のうちに摘み取ろうということですね。まだ第一次世界大戦が続いておりましたから、ロシアはドイツとも戦っていた。それ以外に、イギリスとかフランスとかアメリカとかさらには東から日本も加わって、合計14ケ国に攻め込まれるいわゆる国内戦の時代がはじまるわけです。これが1918年から正確には22年まで続きます。最後まで残っていたのは日本から行った軍隊で、それがシベリアから撤兵したのが22年。なお、樺太には25年まで残っていたので、日本が一番しつこくソビエトに攻め込んでいたわけです。他の国の軍隊は、大体20年ぐらいにはソビエトの労農赤軍によって押し返されて、海外に追放されている。その間は、映画を作るといってももちろん全然設備も無ければ、条件も無いわけですけれども、そのなかでごく自然な成り行きとして、国内戦の状況をニュース映画、記録映画が捉えはじめた。劇映画につきましては、普通の劇映画は作れないので、二巻もの三巻ものの短編が作られている。アギトカと言われていましたが、アジテーション・プロパガンダ、そういう劇映画しか作れなかったわけです。しかし、まだ国内戦が続いている1919年8月に、ソビエト政権の指導者であるレーニンが映画産業の国有化を宣言します。これはもの凄く早いんですね。実はその四ヶ月前にハンガリーでも革命が起きまして、ハンガリーの革命政権が映画産業を国有化するんですが、これは三ヶ月しか続かなかった。レーニンが1919年の8月末に国有化を宣言した後、9月1日には早くも世界で最初の国立映画学校が開設されています。やはり帝政時代からの映画人であったウラジーミル・ガルジンだとか、先ほど名前を挙げましたレフ・クレショフだとかが先生になって、新しいソビエトの映画人養成に乗り出すわけです。それからすでに80年経っているんですけれども、残念ながら我が国には国立の映画学校は無いですね。ヨーロッパの国々で国立の映画学校ができるのは大体1930年代の後半からなんです。ですから、レーニンが映画についていかに先見の明を持っていたかということが分かります。
国内戦が一段落しますとソビエトの国産映画が急速に発展していきます。非常に面白いのは、レーニンの時代とスターリンの時代、特に1930年代以降のスターリンの時代とを比べると非常に大きな違いがあるんです。レーニンは映画を国営にしたんだけれども、映画の作り方だとか内容については自由な政策をとっていたんですね。そういうリベラルな政策から、皆さんがご存知のエイゼンシュテインの『戦艦ポチョムキン』だとかプドフキンの『母』だとかドヴジェンコの『大地』だとか、世界映画史上のベスト10に必ず入るような大名作を含むソビエト映画の黄金時代が到来します。国有化と言っても、国が映画を宣伝の道具にするという意味合いよりも、映画を金儲けの手段から社会の手に取り戻すというのが基本の趣旨だったわけです。ですから、映画人は、客が来なかったら次の映画は作れるかどうか分からないといったことを心配するのではなくて、どうすれば観客に愛され、しかも観客の心と頭に新しい精神を吹き込むことができるか、新しい思考を伝えることができるか、つまり、どうしたら文化、芸術としての映画を質的に高めることができるかということを考えるようになるわけですね。レーニンは、文化、芸術に役人があまりうるさいことを言ってはいけないと言っていました。彼は1924年に亡くなります。ちょっと亡くなるのが早すぎたんですけれども、レーニンが言ったことは、彼の親友でもあり文部大臣でもあったアナトーリー・ルナチャルスキーが受け継ぎまして、1928年にスターリンの独裁体制が確立するまでは、レーニン的な考え方がまだ芸術のポリシーに生きておりました。それをソビエト映画の歴史と見比べてみますと、黄金時代と言われる時期にちょうどピタッと一致するわけです。このことは映画だけでなくて、文学でも美術でも建築でも音楽でもあらゆる文化、芸術に当てはまります。例えば、マルク・シャガールは革命のときにポーランド国境近くのヴィテブスクにいたんですけれども、彼は自ら進んで革命政権のために美術学校を作るんですね。そして、才能ある労働者や農民に絵を描く術を教えることに全力を注ぐわけです。そして、その町で行われた1918年の革命一周年のデモでは、シャガールが下絵を描いた絵の幟を掲げて労働者が行進します。シャガールは「わが回想」という自伝でそのことをとても快い記憶として書き残しております。シャガールはそれから間もなくしてロシアを離れます。確かにソビエト政権の官僚主義によって身動きができなくなった面もあるみたいですが、カジミール・マレーヴィチやワシーリー・カンディンスキーとの美術教育をめぐる意見対立にほとほと嫌気がさしたということもあるようです。それから、カレル・ライスが監督した『裸足のイサドラ』という映画がありましたが、あのアメリカのダンサーのイサドラ・ダンカンのダンス学校の創立を、国内戦で厳しい時期にあったソビエト政権、明日潰れるかもしれないと言われていたソビエト政権が受け入れるわけですね。そういう一、二の例をとりましても、ロシア革命というものが国内外のあらゆるジャンルの芸術家にとってどれほど輝かしく見えたかということがお分かりいただけると思います。もちろん革命と国内戦のときには色んな厳しいことや困難なこと、残酷なことがたくさん起きました。それを否定するつもりは毛頭ありません。
ソビエトが解体してから、スターリンが悪い、いやレーニンが悪い、そもそもは革命が悪いんだ、だから皇帝時代の方が良かったと、どこまでもどこまでも遡っておかしくなっている人たちがいるわけですけれども、昨年、エイゼンシュテイン・シネクラブが中心になって招待しましたロシアの天才的なアニメ作家ユーリー・ノルシュテインが記者会見でこうはっきり言っていました。「私はソビエト体制下でアニメ作家になったから、検閲だとか色んなことで随分と苦労をした。しかし、今のロシアのエリツィンの政府みたいに、子どもたちのことや文化、芸術のことを一切考えていないのに比べたらよっぽどマシだった。それから、今はロシア革命を悪く言えば幅がきくような傾向があるけれども、私はそうは思っていない。ロシア革命の後の一定の期間、あれだけ凄い芸術があらゆるジャンルで一気に噴き出したのは、革命を抜きにしては考えられない。その意味において、私は今もロシア革命を支持します」と明言したんですね。『話の話』だとか『霧につつまれたハリネズミ』だとか、ノルシュテインの心優しい美しくて幻想的で詩的な映像が思い浮かばれるかと思いますが、彼のような人が今でもロシア革命を大切に思っているということが、逆にあの時代がどういう時代だったかを示しているような気がいたします。
エイゼンシュテインにしてもクレショフにしても、あの時代の第一線の映画人たちが最初に夢中になったのはアメリカ映画ですね。当時、国産映画がまだわずかしか作られていなかったときに、その何倍もの外国映画が上映されていました。そのなかでも圧倒的に多いのはアメリカ映画だったんですね。レーニンが、よっぽど退廃的なものとか、あるいは反革命の宣伝でないかぎりは思い切って娯楽映画を幅広く公開してよろしいという政策をとったこともあって、アメリカ映画、特にスラップスティック・コメディ、西部劇、冒険活劇といったものが大量に輸入されたわけですね。この時代は国営化がまだ十分に進んでいませんでした。国内戦の後、1922年から1928年までNEPという新経済政策がとられます。時間がありませんから細かい説明はしませんが、要するに、市場経済を導入して国内戦で疲弊したソビエトの経済を生き返らせようとレーニンがしたわけですね。この政策が実を結ぶまでにはもう何十年もかかるよとレーニンは言っていたんですけれども、1928年にスターリンがこれを中断して、そして一気に中央集権的な統制経済に移行したところにソビエトの悲劇のはじまりがあるわけです。ですから、NEPの時代は、国は映画を作るお金を出すけれども全額出すわけじゃない。ある程度は自分でスポンサーを見つけてこなくてはいけない。外国と合作してもよろしいというようなことがありました。例えば、メジラブポムフィルム。メジというのは国際という意味で、ラブというのは労働者という意味なんですね。それからポムというのは救助、助けるという意味で「国際労働救援会」という組織の映画部みたいなものができまして、特にドイツとは何本も合作映画を作っています。そういうこともこの時代にはありました。メジラブポムフィルムのなかの一番の変わり種と言ってもいいのが、『メアリー・ピックフォードの接吻』ですね。これはこの映画祭で上映されますから、ぜひご覧になってください。この作品については、話だけは聞いていましたが、本当にそんなものを作っていたのかなあと実物を観るまでは信じられませんでした。サイレント時代のアメリカ映画のスーパースター、ダグラス・フェアバンクスとメアリー・ピックフォード、この二人が1920年に結婚をして、ヨーロッパへ旅行に行くんですね。1926年にベルリンに行ったら、ちょうど『戦艦ポチョムキン』を上映していた。凄い評判だったんで、彼らは観たわけですね。それで吃驚仰天する。こんな凄い映画はハリウッドで観たことがないと。こんな映画を作った人に会いたいと。こんな映画を作っている国に行ってみたいということですね。それで七月に予定を変更してモスクワを訪問するんですね。先ほど言いましたように、当時はメアリー・ピックフォードやダグラス・フェアバンクスなどが出演しているアメリカ映画がソビエトの映画ファンの間で大変な人気だったわけですから、これはもう滅茶苦茶の大歓迎になったようです。そのときに、ソビエトの映画人たちが二人にちょっと30分だけ映画を撮らしてもらいたいと言ったんですね。二人がちょうど撮影所を訪問することになっていたので、30分だけ撮らせてくださいと言って、30分だけ撮ったんですね。ところが一年経ったらですね、30分だけ撮ったフィルムとダグラスとメアリーのモスクワ訪問を伝えたニュース映画とを劇のなかにうまく放り込みまして、一本の映画ができている。メアリー・ピックフォードと映画館の切符切りの青年が撮影所で接吻する場面まで映っている。ちょっとサービスでやってみてくれと言って、メアリーが接吻したのがそのまま映画に使われたようです。ですから、メアリーもダグラスもそんな映画ができているということは知らなかったらしいですね。もちろん後から聞いたでしょうが、帰国してからもこの映画については一言も言っていません。昨年亡くなられた淀川長治さん、私も色々とお世話になった人間の一人ですけれども、淀川さんにこういう映画があるのをご存知ですか? と聞いたら、ううん、知らないよ、と仰るわけです。アメリカ映画については生き字引と言ってもいい淀川先生でも知らなかったダグラスとメアリーが出演したソビエト映画があるんですね。ダグラスとメアリーがなぜこの映画について一言も言わなかったのかと言うと、たぶん出演料がタダだったからだと思いますね。当時のダグラス、メアリーは出演料が何十万ドル、何百万ドルのスーパースターですから、タダで映っちゃうのは具合が悪いわけでして、マネージャーが黙っているわけにはいかなかったでしょう。そんなこともあって、敢えて口を閉ざしたんだと思います。今はこの作品は世界各地でノンコマーシャルで上映されておりますから、アメリカでもかなり有名になっているはずです。
ボリス・バルネットの映画なんかにアンナ・ステンという女優が出演しております。この人はロシアからドイツへ行って、それからアメリカに渡る。別に亡命したわけでもないのに、その後のスターリンの時代には考えられないような感じで自由に行き来して、異国に住み着いちゃったわけです。そういう人生が十分にあり得た時代だということですね。そういった自由な雰囲気というのが芸術にはとても大切なんです。レーニンが亡くなった後の1925年にロシア共産党、当時はまだソビエト共産党と言っていなかったので、ロシア共産党、ボリシェヴィキが正式な名前ですけれども、そのロシア共産党の文芸政策というのが発表されます。レーニンが死んだ後ですが、レーニンの考えが大体そのまま採用されている。そこで何を言っているかと言うと、要するに、われわれはプロレタリアートの政権である、労働者や農民の政権であるから、今まで文化や芸術に親しむ機会が無かった労働者や農民が芸術を学び、その才能を発揮できるような条件を作る。しかし、出来た作品については、例え労働者が作ったものであれ、そうでないインテリが作ったものであれ、差別はしない。一切は自由競争だという自由競争宣言というのがありまして、党と政府は、例えプロレタリアートの作品であっても特権は与えないということを言うわけですね。後のスターリン時代を考えれば信じられないような思い切った方針だったわけです。色々と面倒はみるけれども、出来上がった作品については、良いものは良い、悪いものは悪いんであって、例えどんな革命家が作ろうが、労働者や農民が作ろうが、そのことは評価の基準にならないということを言ったわけです。そういった色んな条件が20年代のソビエト映画の黄金時代を作り出したんですね。例えば、アブラム・ロームのその時代の映画に『ベッドとソファ』というのがあります。それから30年代の半ばには『未来への迷宮』という、ずっと上映禁止になっていて、つい最近やっと日の目を見た映画があります。特に『ベッドとソファ』は今観ても大変新鮮ですし、非常に自由ですね。二人の労働者と一人の女性の一種の三角関係でして、当時は非常に住宅事情が悪くて、一つの部屋にこの三人が同居しなければならない。その間に性的関係の行き違いと乱れが起きて、子どもができる。どちらの子どもか分からないという話だけれども、その女性は子どもを産んで自力で育てていく決意をして、独り立ちしていく。今日のフェミニズムの走りになるような内容でもありまして、今観ても非常に新鮮です。20年代のソビエト映画にはやはりもの凄い高揚があったんですが、黄金時代と呼ばれたのにはそれだけの条件があったんだということをぜひ心得ていただきたいと思います。
残念ながら、1928年になりますと、当時の党にはまだスターリンに対してブハーリンだとかトロツキーだとか対立派がいたんだけれども、スターリンがこれを捩じ伏せて専政的な権力を確立します。その28年にせっかくのNEPを上から断ち切りまして、これは上からの革命と言われているんですけれども、農民は強制的に集団化して、都会における工業化を強引に進めていく方針に転換いたしました。レーニンは、その八割が字も読めない農民が文化的に豊かにならなければ、新しい工業を土台にした近代的な社会などできるわけはないとして、急ぐな、急ぐなと繰り返し言っていたんですね。だけれども彼が早く死んじゃったものですから、その後、スターリンは徹底的に急ぎに急いじゃって、反抗する者は直ちに処刑するか強制収容所に送るという暗い時代が30年代にやってくる。同時に映画はすべて国有化して、国有化自体が悪いわけではないんですが、イデオロギーの統制も一緒に行うわけですね。つまり、自由競争ということを宣言した方針が一擲されます。まず、1934年に文学の方で新しい作家同盟ができます。それまで色んな団体、色んな流派があったんですが、それを全部一本化しちゃった。文学の創作方法としては社会主義リアリズムだけが正しい、と。詳しい説明は省きますが、上から公式を押し付けて芸術活動なんかできるわけがない。だけれども、その公式を上から押し付けて、それをはみ出すともう作品が出版されない、映画は上映できないという時代がやってくる。それが30年代なんですね。
20年代に世界的に注目されていたエイゼンシュテインやプドフキンなんかの作品、それから記録映画ではジガ・ヴェルトフという先駆者がいますけれども、このヴェルトフなんかの作品も社会主義リアリズムにそぐわないと徹底的に批判される。エイゼンシュテインは1929年から32年まで正式の許可を得て海外を旅行する。ところが、帰国したらそんな風になっていて、1938年の『アレクサンドル・ネフスキー』までエイゼンシュテインの作品は日の目を見ないわけなんですね。30年代はスターリン時代と言われて、映画の方でも世界的にあまり高く評価されていませんが、この「ロシア・ソビエト映画祭」の準備のために、これまで目を向けられていなかった作品をできるだけたくさん観ました。そうすると、ちょっと想像と違うところがあることが分かってきたんですね。例えば、グリゴリー・アレクサンドロフの『ヴォルガ・ヴォルガ』だとか『サーカス』といったミュージカル映画が大全盛なんです。このミュージカル映画の大全盛はまた色んな条件の結果でして、一筋縄ではいきません。第一に、スターリンも実はアメリカ映画が大好きだった。クレムリンの試写室に外国映画を片っ端から持ってきては、皆で観ていた。コンチャロフスキーの『映写技師は見ていた』で描かれていたとおりで、あの映画には『サーカス』のワンシーンも映っておりました。スターリン自身、アメリカの活劇とかミュージカル映画が好きでしたし、ハリウッド映画が何でこんなに人気があるのか、世界中の観客に受け入れられているのかをソビエトの映画人はもっと勉強しろ、ということでもあったんでしょうね。ならばもうちょっと自由に作らせれば良かった、と私なんかは思うわけですけれども。シナリオの段階からもの凄い検閲をやって、ああでもない、こうでもないとやったわけですから。そういう時代に頭角を現してきたのが、『サーカス』や『ヴォルガ・ヴォルガ』を作ったグリゴリー・アレクサンドロフです。彼はずっとエイゼンシュテインの助監督をしていて、1933年の『陽気な連中』で監督として独り立ちしました。この『陽気な連中』が完全なミュージカルなんですね。その後、『サーカス』だとか『ヴォルガ・ヴォルガ』なんかでもう大変なヒットメーカーになるわけです。それから、スターリンの時代に、ソビエトにハリウッドを作ろうという計画があったんですね。南の方のクリミア半島の辺りにヤルタというリゾート地帯がありますけれども、そこにハリウッドに負けないような大撮影所を作る。南ですから非常に気候もいいし、雨もあんまり降らない。ハリウッドに似ていると。そういう計画もあったぐらいですから、ミュージカル映画が現れてもおかしくないような雰囲気があったわけです。スターリン時代はともかく徹底したプロパガンダの映画が増えてくるわけですけれども、一般の観客もそういうものを喜んでいたということもありまして、そういう観客の要求を無視することもできなかったという面もあります。スターリン自身が娯楽ものに関しては割合、寛容であったということもあって、この時代でも結構面白い映画が作られているわけです。『サーカス』なんて、30年ぐらい前にはじめてソビエトで観たとき、こんな面白い映画を作っていたのかと驚きましたね。アメリカ映画を実に良く勉強しているわけです。場面転換から俳優の演技のつけ方から、実にスマートな映画になっています。『ヴォルガ・ヴォルガ』の物語展開にもアメリカ映画の影響がうかがえます。1920年代のエイゼンシュテインやプドフキンもアメリカ映画から多くを学んだんだけれども、実は1930年代もやはりアメリカ映画から大きな影響を受けている。それは非常に面白い歴史の事実なんですね。
しかしながら、映画をめぐる状況はやはり基本的にはどんどんどんどん悪くなってくるわけです。エイゼンシュテインも苦労します。今回の映画祭の上映作品には入っておりませんけれども、クレショフのグループにいたボリス・バルネット、彼が作った『騎手物語』は競馬の話でして、馬を一生懸命育てている少女とおじいちゃんの物語なんですが、これが何と戦後までずっと検閲で引っかかっていた。内容的に反ソビエト的とかいうところは一切無いわけですから、何で検閲に引っかかっていたのかまったく理解に苦しみます。白石かずこさんが仰っていたのですが、これはきっと検閲をやっている役人がこんなにものびのびとした映画を作っていることにやきもちを焼いたんじゃなかろうかと。私もそのやきもち説に賛成です。確かに嫉妬を感じるぐらいしなやかな映画的感性に溢れた作品なんです。以前にアテネ・フランセ文化センターで上映しました『ノヴゴロドの人びと』というバルネットの戦争中の抵抗映画があるんですけれども、これも上映禁止になったんですね。立派な抵抗映画なんですけれども。その理由を考えると、やっぱり凄く自由に映画を作っているということしか考えられない。全て上から締め付けられたスターリンの時代は大量粛正も行われていた暗黒の時代で、苦しめられて自殺した人もあれば収容所に放り込まれて殺された人もいるんだけれども、そういう暗い時代においても映画を作る人たちの映画への愛情と言いますか、映画的感性と言いますか、芸術への良心といったものは決して死に絶えていなかったということです。スターリン主義を批判することは正しいし、あの時代を二度と繰り返してはいけないんだけれども、前の時代との断絶ばかりを強調して、あの時代の映画は全部ダメだったと片付けてしまうわけにはいかない。そのことは、私がこの映画祭をコーディネートして改めて勉強したことであります。
この講演の後で参考上映します『虹の世界のサトコ』という映画は1950年代の半ばに日本で一度公開されています。制作年は1952年で、原題は『Sadko』です。リムスキー=コルサコフのオペラの「サトコ」を、あの音楽を使って、一種のメルヘンとして映画化したわけです。ミュージカルではないですけれどもね。オペラ映画でもないです。この映画は淀川長治先生が大変気に入っていらっしゃいました。淀川先生にはご無理を願ってエイゼンシュテイン・シネクラブの発起人になっていただきまして、お亡くなりになるまで顧問をやっていただいたんですが、例会にもお越しいただいてお話をしてもらったことがあります。そのときに仰っていたんですが、最初にニューヨークにいらっしゃったときに、ロシア映画の専門館があるというのでお寄りになったそうです。ロシアの色んなサモワールがロビーに置いてあったりして、小さいけれども雰囲気がとても良かったと。そこで何本か映画をご覧になったようですが、そのうちの一本がこの『Sadko』だったんですね。私はソビエト映画の紹介なんかをやっているものですから、山田さん、『Sadko』を日本に絶対持ってきてください、とやいのやいのと言われていました。たまたまソビエト映画をビデオで発売したいという会社がありまして、何か良い映画を推薦してほしいと言われたものですから、これは良い機会だと思って、淀川先生のたってのご希望である『Sadko』を推薦して、ニュープリントを取り寄せたんですね。ですから、今日これから上映するのはそのときのプリントです。字幕が入っておりませんけれども、もともとそんなに難しいお話じゃ全然ございませんから、ごゆっくりお楽しみください。良い意味で非常におおらかな映画でして、色彩がきれいで、音楽もたっぷり入っていて、今の水準から見れば決して上手とは言えないけれども特撮を使ったスペクタクル場面も結構あります。オペラ「サトコ」で一番有名な「インドの歌」の場面、象を連れたたくさんの兵隊の前で、人間の顔をした鶏みたいなものが歌を歌うと、象も兵隊も皆眠ってしまう、淀川先生が面白い面白いと盛んに仰っていたあの場面もありますからご覧になってください。この映画の監督のアレクサンドル・プトゥシコという人は、もう亡くなりましたけれども、ソビエト映画史では非常に重要な人です。ソビエトのアニメーションの創立者の一人ですね。アニメーションと特撮を使ったメルヘンの映画で大変有名になった監督です。戦後すぐに日本で公開された『石の花』というカラー映画がありましたけれども、ウラル山脈に伝わる伝説を特撮を使って映画化した作品です。大変素朴な作品ですけれども、捨て難い味わいがあって、淀川先生も大変お好きでした。その『石の花』の監督もプトゥシコです。彼は30年代に『新ガリバー』という非常に有名な作品も作っております。「ガリバー旅行記」に「新」を付けているわけで、「新ガリバー旅行記」という意味なんですね。『新ガリバー』は、ピオネールの少年が「ガリバー旅行記」を読んでいるうちに眠っちゃって、夢のなかに「ガリバー旅行記」の世界が現れるという仕掛けです。少年がガリバーになるわけですけれども、小人が全部人形なんですね。これが凄いわけです。無数の人形と人間のライブ・アクションを組み合わせたモノクロ映画ですが、当時としては非常に大胆な人形アニメと言っていいでしょうね。小人たちが王様に搾取されていて革命を起こすと、それをガリバーである少年が助けるというところが、ソビエト版「ガリバー」ならではなんですけれども。そして、最後に目が覚めて、現実に戻るという物語です。そういう映画を作っている人ですからなかなか多才でありまして、『ルスランとリュドミーラ』とか『サルタン王物語』とか、ロシアの民話、伝説を随分映画化しております。この『虹の世界のサトコ』が作られた1952年というとスターリン時代の末期ですけれども、この手の映画にはほとんど制約が無かったということも分かります。プトゥシコは、『石の花』がカンヌ映画祭で色彩賞を受賞したように国際的にも大変注目された監督ですので、この機会に、特に若い方はご覧になっていないはずなので、ご覧いただいて、こんな映画もあるんだなあと楽しんでいただければと思います。もう時間ですので、私の話はこれで終わらせていただきます。